ダイバーなら知っておきたいサンゴのこと
第5回:サンゴの産卵

沖縄の島々では5~6月、九州・四国や紀伊半島では7~8月、サンゴの産卵の神秘的な様子が話題となりますが、サンゴって何でしょう?
サンゴやサンゴ礁(※)が地球の環境を守る大事な存在だということは今や小中学校でも学ぶのでご存じの方も多いでしょう。ダイバーなら知っておきたいサンゴのことを6回連載(不定期)でお届けします。
※サンゴとサンゴ礁の違いについては連載第3回をご覧ください。
※2025年8月現在の情報です
サンゴの一生
サンゴの繁殖
サンゴが動物の仲間であることは連載第1回で紹介しましたが、どのように生まれて、育って、成長するのでしょう? 種類によって繁殖の仕方はさまざまですが、大きくふたつに分かれます。
産卵することで仲間を増やす「有性生殖」と、自ら分裂してクローンを増やす「無性生殖」です。ミドリイシの仲間のように両方の方法で増殖できるものもいます。
有性生殖 放卵放精型

ミドリイシの仲間の産卵
写真/森脇純一(ダイビングチームうなりざき)
受精すると数日で赤ちゃん(プラヌラ幼生)となり、潮の流れに乗ってうまくすめる場所にたどり着き、プラヌラ幼生はイソギンチャクのようなポリプとなります。するとサンゴの体に褐虫藻と呼ばれる100分の1mm余りの小さなプランクトンがすみ始め、太陽光で光合成をしてポリプの分裂と骨格形成が繰り返し行われて成長していきます。成長の速いサンゴの仲間では1年に約3cm、育つといわれます。サンゴの種類によってリュウキュウキッカサンゴやコモンシコロサンゴのような巨大な群体をつくるものと、ハナヤサイサンゴのような小ぶりな群体をつくるものとがありますが、巨大な群体になるまでには長い年月がかかることがわかりますね。
なお、産卵ができる大人に成長するには、だいたい3~5年かかるといわれます。
生物の多くに共通する性別も気になります。サンゴには雌雄同体のものと雌雄異体のものがあります。サンゴの産卵でよく話題になるミドリイシの仲間は雌雄同体で、同じ群体から卵と精子が放出されます。

こちらも雌雄異体のキクメイシの仲間。ピンク色の卵の産卵間近
写真/マリンフォトライブラリー
同様に深海にすむ宝石サンゴと呼ばれるアカサンゴ、モモイロサンゴ、シロサンゴも雌雄異体で、産卵時には卵と精子を海中に放出する繁殖様式をもちます。ハマサンゴの仲間やシコロサンゴの仲間も見た目はまったくわかりませんが、一斉にもやもやとした精子を放出する群体と、卵だけを放出する群体があります。不思議ですね。
雌雄同体も雌雄異体も「放卵放精型」です。
有性生殖 幼生保育型

ハナヤサイサンゴの仲間。産卵シーンではありません
写真/後藤ゆかり
私たちが映像でよく見るサンゴの産卵は、前述の放卵放精型ですが、一方、体内で受精して幼生(プラヌラ幼生)を放出するサンゴもいます。このタイプを「幼生保育型」といいます。種類としてはハナヤサイサンゴの仲間とミドリイシ科のフトエダミドリイシが知られるところです。放卵放精型のサンゴは一年に1回しか産卵しないのに対して、幼生保育型のサンゴは毎月、月齢周期に合わせて幼生を放出するというから驚き! ただし、日本の海域では石垣島では毎月幼生の放出が確認されていますが、沖縄本島では夏季の数カ月のみしか確認されていないことから緯度が低く、水温の高い海域でのみ毎月幼生が放出されていると考えられています。
無性生殖

サンゴの植え付け用のサンゴの株を育てている沖縄の海中
写真/後藤ゆかり
波や何かの衝撃で折れてしまった破片が再び着底するとクローンをつくりながら成長していきます。成長のスピードは種類や生息する環境によって変わりますが、1年で数cmから10cm以上大きくなることも。この特性を生かし、世界中の熱帯・亜熱帯地域の海でミドリイシの仲間の植え付けが行われています。
サンゴの産卵時期
潮回りと密接な関連

サンゴの産卵は夜間に行われることがほとんど
写真/マリンフォトライブラリー
サンゴの産卵は夜間行われることが多いので、私たちダイバーは予想時間に合わせてナイトダイビングで産卵ウオッチングに臨むことになります。
夜潜ればいつでも見られるわけではなく、日本では5月頃から9月頃までの春~夏にほぼ限定されます。種類によって時期が少しずつずれるため、水温の高い沖縄の島々ではこの期間にいろいろな種類のサンゴの産卵が毎月見られるようです。また、近年は産卵が確認されているエリアが北へ北へと延びていて、伊豆諸島はもちろん、本州でも紀伊半島、伊豆半島、房総半島などで見られるようになっています。
サンゴの産卵に最も重要なのが月齢。満月または新月の大潮の前後によく見られることが知られています。サンゴの種類や海域によって、大潮当日なのか。大潮の前日または2~3日前なのか、それとも大潮の後なのかは変わるようですが、地元のダイビングガイドさんたちの尽力でそれぞれの産卵予想日が発表されています。サンゴの産卵シーンをご覧になりたい方は、情報を確認して予定を組みましょう。
サンゴの産卵を見てみよう
画像/岩﨑俊哉(南紀シーマンズクラブ)
サンゴの産卵には様々な様式がありますが、国内外のダイビングサービスで「サンゴの産卵ウオッチング」で見せているのは、ミドリイシの仲間、いわゆるエダサンゴやテーブルサンゴなどの産卵シーンが圧倒的に多いようです。ガイドさんがいろいろなサンゴをリサーチし、ミドリイシ系以外の見ごたえのある種類を見せてくれることもたまにありますが。暗い海の中に一斉にサンゴの卵が舞い上がっていく様子は何度見ても飽きません。上の画像は紀伊半島の南部(南紀)串本で2025年7月に撮影されたもの。あちらでもこちらでもプワーーーーッとサンゴの卵が放たれていく様は、圧巻ですね。
沖縄の西表島では9月頃まで見られるといいますし、紀伊半島や伊豆半島、房総半島などでも9月頃に見られる種類もあるとか。ぜひチェックして見に出かけてみては?
文/後藤 ゆかり(MDWデスク)







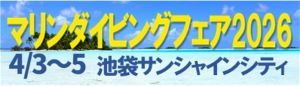


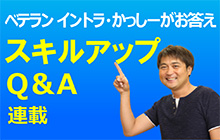

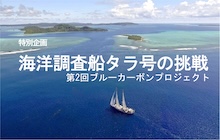
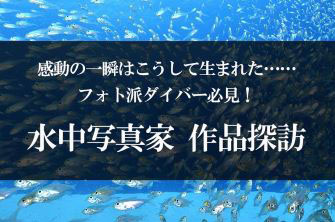






 マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!
マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!