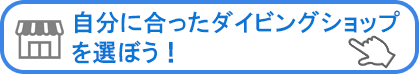ダイビングショップ選びなら「マリンダイビングWeb」
ダイビングライセンス(Cカード)を
徹底解説!

本格的にダイビングを楽しもうと思ったら、講習を受け、ダイビングの資格、つまりダイビングライセンス(Cカード)を取得する必要があります。ダイビングライセンス(Cカード)とは何なのか、取得するための講習ではどんなことをするのか、かかる費用は?など、詳しく解説します。
ダイビングライセンス(Cカード)とは?
「ダイビングライセンス」は、正確には「Cカード」と言います。「Certification Card」の略で、日本語にすると「認定証」の意味。ダイビング教育機関による講習プログラムを受講し、必要な知識とスキルを身につけた証として発行されますが、ダイビング教育機関は民間の団体なので、国家資格(免許)ではありません。ダイビングサービスの施設を利用したり、タンクをレンタルしたりする際には、このダイビングライセンスの提示が求められます。所持していないとダイビングできないこともあります。これは国内外、どこでも共通です。

Cカードはダイビング教育機関によって発行されます。画像はPADI(左)、SNSI(右)のCカード
ダイビングライセンスは、ダイバーとして身につけておくべき知識とスキルを習得したことを証明するものです。しかし最初に受けた講習だけで、オールマイティにどこの海でも潜れるというわけではありません。最初に取得するのは、オープンウォーターランクのCカードで、これは昼間の比較的穏やかな水域で、最大水深18mまでで減圧停止をする必要のない範囲なら潜れるなどの規定があります。さらにいろいろな海を潜るためには、継続して講習を受けて、上のランクのCカードを取得する必要があります。
また、しばらくダイビングをしていないとスキルは低下し、知識も忘れてしまうことがあります。そのため、前回のダイビングから期間が空いてしまった場合は、リフレッシュコース(教育機関によって名称は異なる)を受講することが推奨されています。
ライセンスを取得した後も、継続的にダイビングを行い、スキルを磨いて知識を深めていくようにしましょう。
ダイビング教育機関とは?
ダイビング教育機関とは、その名の通りダイビングを安全に楽しむためのルールを「教育」する「機関」のこと。より多くの人がダイビングを楽しめるように、講習カリキュラムや教材を作成したり、ライセンスカード(Cカード)を発行したりと、さまざまな活動をしています。そして、それを教える教室がダイビングショップ、教える人がインストラクターです。ダイビング教育機関は複数あり、ポリシーやカリキュラムが異なります。ダイビングを始める際には、教育機関によっての違いを知り、自分の好みに合った教育機関に所属するダイビングショップ、インストラクターの講習を選ぶといいでしょう。
ダイビングライセンス(Cカード)取得講習の流れ
学科講習
学科講習では、ダイビングを安全に楽しむために必要な知識を身につけます。水中と陸上の環境の違いやダイビング器材の扱い方、ダイビング計画の立て方などを習います。マニュアルや映像を使ってインストラクターが楽しく教えてくれるので、「勉強が苦手」という人でも心配ありません。学科講習の最後には簡単なテストがあり、知識がきちんと理解できているかを確認します。

(写真提供/SNSIジャパン)
所要時間は教育機関やショップによって異なりますが、5~10時間程度が一般的。パソコンやスマートフォンで学習できるeラーニングで受けることも可能なので、なかなかショップに行く時間がない忙しい人でも大丈夫です。
限定水域(プール)講習
浅いところで
まずは足がつく浅いところで、器材の使い方からスタート。ダイビングは器材を使いこなすことで、より安全に&快適に水中を楽しむことができます。まずは器材のセッティングから始め、準備ができたら水の中へ。フィンを使った泳ぎ方、マスクに水が入った時の対処法など、さまざまなスキルを練習します。

マスクの中に水が入ってしまったときの対処法「マスククリア」。ダイビングを安全に楽しむために必要なさまざまなスキルを習得します
深いところで
浅いところで練習をして水に慣れてきたら、水深4~5mほどの少し深いところに移動。潜降や中性浮力といった実践的なスキルを練習します。限定水域(プール)講習が終わるころには、水中を自由に泳ぎ回れるようになり、海洋実習に行くのが待ち遠しくなるはずです。

浮力コントロールをマスターすると、水中を自由自在に泳ぐことができます。浮きも沈みもしない「中性浮力」は、まるで無重力で宇宙を漂っているよう
海洋実習
最後はいよいよ海でのダイビング。一般的に2日間かけて行なわれる海洋実習は、限定水域(プール)講習で身につけたスキルが、海でもちゃんと実践できるかを確認する場。落ち着いて行えば、まず問題はないはずです。それさえクリアすれば、あとは水中世界が楽しめます。海洋実習が終わって1~2週間ほどすると、ライセンスカード(Cカード)が手元に届きます。これであなたもダイバーの仲間入り。世界中の海でダイビングを楽しみましょう!

海洋実習もコンディションの良い穏やかな海で実施されるので安心。海の世界を満喫しましょう(写真提供/PADIジャパン)
ダイビング教育機関でダイビングショップを選ぶ
前にも述べたように、ダイビング教育機関によってポリシーやカリキュラムに違いがあるます。ライセンス取得のためのダイビング講習は、各教育機関の作成したカリキュラムに乗っ取って、その教育機関に所属するインストラクターから受けることになります。
日本国内にあるダイビング教育機関については、Cカード協議会のウェブサイトにまとめて掲載されています。Cカード協議会は正式名称を「レジャーダイビング認定カード普及協議会」といい、日本国内の主要なCカード発行組織14社によって構成されている団体です。どんなダイビング教育機関があるかは、こちらでチェックしましょう。
ダイビングライセンス(Cカード)に関するQ&A
ダイビングライセンス(Cカード)は何歳から取れる?
講習を受けてダイビングライセンス(Cカード)を取得するには、多くの教育機関で成長期における水圧の影響などを考慮して年齢制限が設けられています。10歳以上というのが一般的です。また、PADIのように10歳以上15歳未満は「ジュニア・ダイバー」認定として、講習中の最大深度や認定後の活動に年齢による制限を設けている教育機関もあります。
ダイビングライセンス(Cカード)取得にかかる費用は?
各ダイビングショップで、講習料金は異なります。この違いは、講習にかかる費用のどの部分が含まれているかでかなり大きく変わります。ウェブサイトや広告などに表示されている講習料金には、かかる費用のすべてが含まれていない場合もあるので、事前に確認するようにしましょう。
ダイビングライセンス(Cカード)は一生モノ?
ほとんどのダイビング教育機関では、ライセンス(Cカード)の更新制度はとっておらず、一度取得すれば、一生有効なものとなります。ただし、しばらく潜っていないとスキルや知識を忘れてしまうので、リフレッシュコースなどを受けることが推奨されます。
ダイビングライセンス(Cカード)を紛失したらどうする?
ダイビングライセンス(Cカード)は、ダイビングを楽しむのに必要な知識とスキルを身につけた証明書なので、紛失してしまうと潜れなくなってしまう可能性も。カードは再発行できるので、まずは自分が講習を受けたダイビングショップに相談を。ショップがすでに閉店していたり、わからなくなってしまった場合は、カードを発行しているダイビング教育機関に直接問い合わせを。
自分に合ったダイビングショップを選ぼう
東京都大島町
フィッシュアイランドクルー
TEL:04992-2-0123

体験からプロダイバー講習まで講習専門店
「講習もやっています。」というショップではありません。体験ダイビングからプロコースまでPADIコースを開催。PADIコースディレクターが常駐しています。エンリッチドエア充填設備有りで、エンリッチドエアダイバーSPも即日受けられます。リブリーザーダイバーコースも開催しています。趣味ダイバーから職業ダイバーまで対応できます
東京都千代田区
ダイブ クラップス
TEL:03-6909-7701

アットホームな都会派ダイビングスクール!
しっかりと楽しく簡単に上達!インストラクターコースも手掛ける上級インストラクターのみ在籍!ツアーも宿泊先にこだわり、オーナーが大好きな露天風呂があるホテルにしか泊まりません・・・ツアー帰りは美味しい地元のご飯で満腹!さぁ!是非、クラップスへ!無料説明会毎日開催!
東京都千代田区
ココナッツ東京店
TEL:03-5256-9981
〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-19白須ビル1F ![]()

始めようと思った瞬間がスタートライン!
ダイビングスクールココナッツ東京店は創業してから37年間無違反・無事故を更新中です!また、最高峰PADI5スターCDCに認定されているダイブセンターは国内で3店舗のみ!その1店舗がココナッツ東京店になります。より安全・安心な講習をご提供します。始めてみようと思ったその気持ちが大事です!一緒にダイビングライフ楽しみましょう!
東京都中央区
パパラギダイビングスクール東京店
TEL:03-6214-3880

パパラギで始める、海のあるライフスタイル
流氷からサンゴの海まで年間1,000本以上のファンダイビングツアー。どんどんダイビングが上達するステップアップコース。海の不思議や環境を学ぶセミナー。そして、たくさんの仲間とつながる豊富なイベント。海を愛するプロスタッフが、あなたに最高のダイビングライフを提供します!ダイビングが久しぶりの方も安心のコースも開催中です!
東京都荒川区
ダイビングショップ グラッド
TEL:03-6807-9206

休日をのんびり、優雅に過ごす
少人数で一人一人を大切に!Cカード取得講習やFUNダイビングツアーにて1人1人が楽しめることを第一にご案内いたします。ダイビングを始めたい方・ライセンスをすでにお持ちの方、旅行前のリフレッシュダイブをしたい方などお気軽にご相談ください。範囲に限りはありますが、皆様のご都合の良い場所や最寄り駅での集合・解散が可能です。
東京都墨田区
マグ ダイビングスクール
TEL:03-3616-0036

スカイツリーすぐそばのショップ!
小さなお店だからこそできるキメ細やかなサービスを心掛けています! そしてダイビングは仲間と和気あいあい楽しめるショップです♪ よく行くエリアは千葉・伊豆方面、1年に何度か沖縄や海外の遠征ツアーなども開催しています♪
東京都江東区
エムズダイビングアドベンチャー東京本店
TEL:03-3820-6877

東京一!安心安全にダイビングが楽しめる!
これからダイビングを始められるみなさまに安心して潜っていただけるよう、少人数制のチームで手厚くサポートいたします。豊富なスキル&ランクアップコース、各ダイビングブランドの取り扱い、ツアー開催場所もメジャーどころから秘境まで数多く取り揃えておりますので、ライセンス取得後も末永くダイビングをお楽しみいただけます!
東京都世田谷区
ブルーアンドスノー
TEL:03-5430-5377
〒155-0033 東京都世田谷区代田2-18-12 ガーデニア代田102![]()

女性1人でも安心のスクール
初めてでも安心!ライセンスが取れる東京のダイビングスクールです。はじめは一人でご来店される方が多いですが、通ううちにすぐに仲間が増えていきます。また取れるライセンスは初心者コースからインストラクターコースまで多種多様。葛西店もあります。
東京都杉並区
Full Moon Diving Adventures
TEL:070-5562-3459

海を身近に感じる都会LIFEを過ごしませんか?
講習やツアーの発着はプライベート、グループツアーならご自宅や最寄り駅送迎が可能です。お一人様でも気の合う仲間とでも、貴方の海遊びライフをサポートさせて頂きます。ツアー・講習は1名様から開催可能。プライベートガイドで貴方のペースでダイビングしましょう!都市型ショップが初めての方も、ベテランダイバーも是非一度お越しください。
東京都豊島区
パパラギダイビングスクール池袋店
TEL:03-6384-7188
〒171-0055 東京都豊島区南池袋1-21-4 繁昌社南池袋ビル4F![]()

パパラギで始める、海のあるライフスタイル
流氷からサンゴの海まで年間1,000本以上のファンダイビングツアー。どんどんダイビングが上達するステップアップコース。海の不思議や環境を学ぶセミナー。そして、たくさんの仲間とつながる豊富なイベント。海を愛するプロスタッフが、あなたに最高のダイビングライフを提供します!ダイビングが久しぶりの方も安心のコースも開催中です!
東京都練馬区
OK MARINE PRO
TEL:03-3993-3824

自社プール完備&64年の実績を誇るスクール
安全に楽しく潜れるようになるためには、技術をしっかり身につけることが大切。でも、技術の習得スピードには個人差があります。OKマリンプロのプールレッスンは、できるまで何回でもOK♪シニア世代も、体力面や水泳に不安な方も、安心してお任せ下さい!
神奈川県横浜市
パパラギダイビングスクール横浜店
TEL:045-320-6868
〒220-0073 神奈川県横浜市西区岡野1-13-5 横浜西口サンエースビル4F![]()

パパラギで始める、海のあるライフスタイル
流氷からサンゴの海まで年間1,000本以上のファンダイビングツアー。どんどんダイビングが上達するステップアップコース。海の不思議や環境を学ぶセミナー。そして、たくさんの仲間とつながる豊富なイベント。海を愛するプロスタッフが、あなたに最高のダイビングライフを提供します!ダイビングが久しぶりの方も安心のコースも開催中です!
神奈川県横浜市
ココナッツ横浜店
TEL:045-663-9981
〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町2-9-2DPM不老町ビル1階 ![]()

ライフスタイルにダイビングをとりいれよう。
ダイビングスクールココナッツ横浜店はPADI全国最優秀賞も受賞経験あり。ココナッツは皆様がダイビングを生涯の趣味として長く楽しんで頂けるように講習性にしっかりとした丁寧な講習を心がけております。日本は北海道から沖縄まで、海外から各地に眠る秘境の地までご案内いたします。
神奈川県三浦郡
湘南DIVE.葉山タンクサービス
TEL:0120-560-777
〒240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色2420-101 ![]()
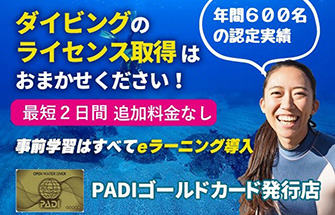
2日間でPADIゴールドカード免許取得!
都内から最短1時間の湘南でPADIのOWD国際ライセンスの取得が最短2日で可能。海まで歩いて3分の自社の海で講習もしやすく低コスト。事前学習は最新のeラーニングを導入。必要経費も全て含んだ価格設定。手話でのサポートもあり。
神奈川県大和市
ピースドルフィン
TEL:046-265-6707
〒242-0021 神奈川県大和市中央3-4-12山口ビル1F ![]()

今年は本気でダイビングを趣味にしよう!!
ライセンスを取得して世界中の海へのパスポートを取得しましょう!ただライセンスを取るだけ・・・ではなく、ピースドルフィンでは自信を持って海を楽しめるダイバーを育成することをモットーとしています。その為、月謝制教育システムを採用しています。
千葉県千葉市
オーシャンドリーム
TEL:043-227-0082
〒260-0018 千葉県千葉市中央区院内1-17-3斉藤ビル1F ![]()

千葉の海であこがれのダイバーになろう!
私たちが大切にしているのは、ダイビングと水中世界が「大好き」という思いです。あこがれのダイビングの夢を一緒に叶えましょう。初心者ライセンス取得コース、プロダイバーまでの各種PADIコースや、千葉の海ダイビングツアーは1名様から常時開催しています。いつでも気軽に遊びに来て下さい。
千葉県船橋市
エムズダイビングアドベンチャー西船橋
TEL:047-401-8188

初心者も安心!1から丁寧にサポートします!
東京で30年の老舗ダイビングショップの支店が西船橋にOPEN!東京と西船橋の2店舗でみなさまのダイビングライフをサポ-トいたします!東京店西船橋店共に女性スタッフが常駐しておりますので女性一人でもご安心いただけます♡ツアーでは千葉・神奈川・伊豆・伊豆諸島をご案内!また、当店でしか開催ができない秘境ツアーなども毎年開催♪
千葉県鎌ヶ谷市
Timon Ocean Fantasy
TEL:047-499-5315

ダイビングしたい気持ちをがっちりサポート
ダイビング初心者~プロコースまで常時開催!ツアーも1名様から開催して、「今ダイビングに行きたい」お客様の気持ちをがっちりサポート!ヨットクルージングの開催もあり、とにかく海で遊ぶことが大好きなティモンです。ヨーロッパを中心とした海外ツアーも多数開催♪併設のスペインレストラン「バルコ・ピラータ」でお酒や食事も楽しめます。
埼玉県春日部市
ダイビングショップ・シーズ春日部店
TEL:048-734-5672

舞台は海!テーマは感動!主人公はあなた!
この体験はあなたの人生を変えてしまうかも。水中世界にはそんな感動があなたを待っています! 女性スタッフ常勤、ライセンス取得コースは全費用込みの安心価格! ライセンス取得から自立してダイビングが楽しめるようになるまでシーズのスタッフがしっかりサポートします!
埼玉県川越市
Marine Club Kawauso
TEL:049-243-9411

遠方のダイビングも当店の無料送迎で快適♪
当店は埼玉県の川越市という海から離れた場所にありますが、埼玉県・東京都から現地ダイビングポイントまでの無料送迎をしており、快適なダイビングライフを提供致します。スタッフ若干名の小さなお店ですが、講習、ツアー、器材販売(展示品・モニター品多数有り)、修理・オーバーホール等、ダイビングに関わる事を総合的に提供しております。
大阪府大阪市
ダイビングショップ潜楽屋
TEL:06-4303-5431
〒543-0052 大阪府大阪市天王寺区大道3-3-11 筆本ビル302 ![]()

もう1度夏休みしませんか?
当店は、入会キャンペーンは実施していませんが、【リピート率90%】を頂いております。お客様の体力にあったペースで相談しながら、無理のないかつ質の高いスクールを目指しているからです。平日も開催しており、どなたにも利用しやすい環境を整えています。危険もともなう遊びですが、『また早く海に行きたい』と思える実習をしております。
大阪府堺市
EDIVER'S
TEL:072-232-5778
〒590-0952 大阪府堺市堺区市之町東2丁1-10-2階 ![]()

お一人様から開催可能!少人数制スクール!
当店では少人数制で丁寧な講習を心がけております。1人1人に十分な時間を取れるのでしっかりとスキルが上達しますよ♪自宅への無料送迎もありますので遠方の方もご相談下さい。講習には丁寧で優しさに定評のあるイントラ歴20年以上のオーナーインストラクターが担当致します。皆様のダイビングライフを末永くサポートさせて下さい♪
兵庫県西宮市
トライブダイビングスクール兵庫西宮
TEL:0798-67-3603

楽しくしっかり習ってダイビングを趣味に!
トライブダイビングスクールは、ダイビングを趣味にして、とびっきりいい海を楽しみたい! とお考えの方に最適な初心者&初級者専門のダイビング教室です! 初心者にとって一番不安な海洋実習が、関西では唯一、3日間あるので一気に上手くなります。
沖縄県石垣市
MOANAダイビングカレッジ石垣島
TEL:0980-87-6212
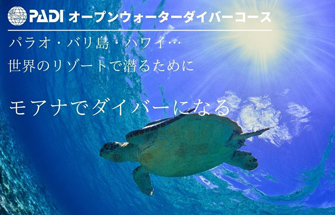
世界のリゾートでも通用するダイバーになる
MOANAは日本最南端に位置する、講習専門の5スターPADIダイビングスクールです。ゴールドカードが発行可能で、創業以来、一貫して少人数制で丁寧な講習をご提供。インストラクター開発も行い、石垣島では唯一PADIコースディレクター経営のスクールです。そのためインストラクターの技術は業界トップクラス! おひとりでも歓迎です。






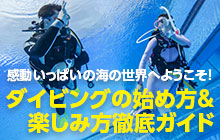







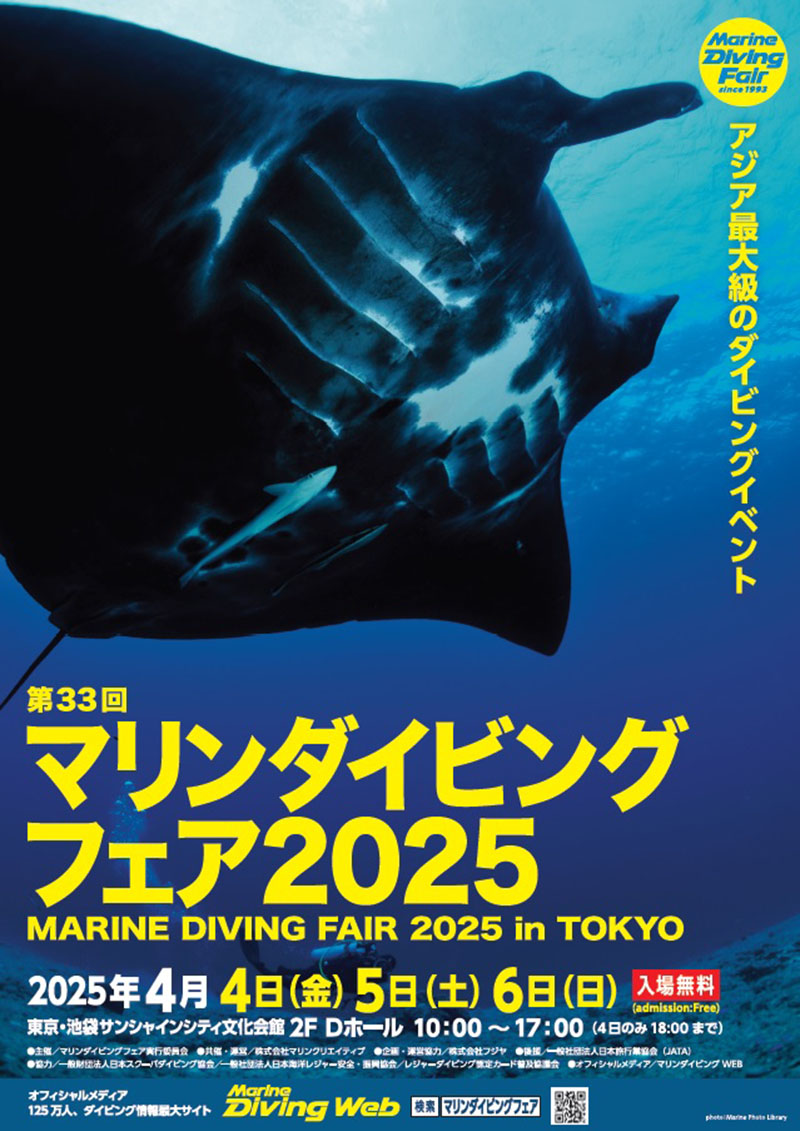












 GULL3点セット+GULL&SCUBAPRO オリジナルボトルをプレゼント!
GULL3点セット+GULL&SCUBAPRO オリジナルボトルをプレゼント!