【新連載】テツ先生の新・海のいきもの
第1回 Fishは魚?

「好奇心を持ち続け、知識や経験を積むことで、同じ風景や生きものが同じように見えることはない」という信念の下、今日も三保真崎の海で生物観察を楽しんでいるテツ先生。東海大学海洋学部、海洋生物学科准教授で、インストラクターでもある先生に、ダイビングのお楽しみ「海のいきもの」の観察について独自の切り口でお話いただく新連載、スタートです。
※2025年9月の情報です
Fishは魚?
「海のいきもの」と聞いて、私(テツ先生)がはじめに思い浮かべたのは魚です。たぶん、ダイバーの皆さんにとっても一番馴染みのある「海のいきもの」は魚ではないでしょうか。
一般的に魚(魚類)と聞くと真横から見て、尾が縦に付いている生きものを思い浮かべますよね。水中で尾が横向きの生きものは、ほ乳類です。

ほ乳類のイルカの尾は横向きで、真横からより、下から見上げると形がよくわかる
Photo by Marine Photo Library

マダイ(英名:Japanese red seabream)水深20m 体長20cm(ナイトダイビングで撮影) 魚は真横から見ると尾の向きが縦。図鑑では基本的に頭が左で尾を右にした状態の写真が採用されます
Photo by Takashi Tetsu
ほ乳類である人間に例えると、尾が該当する部位は足であり、泳ぐ形態から考えると、やはり尾はイルカのように横向きに付いていることになりますよね。
小学校低学年の児童が想像で描く海の中や、水族館内での写生では、まれにサメの尾ヒレがイルカのように描かれていますが、そんなハイブリッドは起こらないと思います(笑)。
英語では一般的に、魚を示す単語は“fish”ですが、これは魚類だけを指しているわけではなさそうです。というのも、ヒトデ(写真1)やクラゲ(写真2)、イカの英名には、形態や形状にfishが付け加えられた名称があります。それ以外の海のいきものはどれも、“Sea”が形態や形状の前に付いた名称になっています。

写真1/ニセモミジガイ(英名:Sand sifting starfish) 水深7m 体長15cm
名前に「ニセ」とあるように、本家「モミジガイ」が存在します。ヒトデなのに「◯◯ガイ」って紛らわしいなぁ〜と思った方もいるでしょう。この近縁には「トゲモミジガイ」という最強のヒトデがいます。な、な、何と!フグと同じTTX(テトロドトキシン)を持っている種がいます。この3種は同じ英名で表記されているので、英名での種別は混同します。
Photo by Takashi Tetsu

写真2/ベニクラゲモドキ(学名:Oceania armata Kolliker)水深20m 体長1cm
名前に「モドキ」とあるように、本家「ベニクラゲ」が存在しています。本家は、何と!不老不死のクラゲとして一躍有名ですが、モドキのほうは残念ながら、最近の研究で「不老不死」ではないことが発表されました。
Photo by Takashi Tetsu
以前、この件について日本語を理解している英語圏のダイバーに、「魚じゃないのになんでfishっていうのでしょうか?」と聞いてみたことがあります。
すると、「Jerry fishやStarfish、Cuttlefishに何でfishが付いているんだ?なんて考えたこともなかったけど、言われてみれば不思議ですね」って同調されてしまいました。
逆に、名前にfishが付かない
“eel”(ウナギ・アナゴ)
“Dragonets”(ネズッポ)
“Barracuda”(オニカマス)
“Blenny”(カエルウオ)
“Gurnards”(ホウボウ)
“Seahorse”(タツノオトシゴ)
といった英名の魚もいるので、英名に“fish”と付ける基準があるのかないのかはわかりません。
皆さんもダイビングライフをスタートさせて、海外に行く機会があれば、現地のインスタラクターやガイドさんに同じ質問をしてみてください。きっと彼らも同じように、「そんな事、考えたこともなかったよ」って言うに違いありません。
ダイバーの皆さんも、自分ならではの視点をもつことで、「海のいきもの」の観察がより楽しくなっていくのではないでしょうか?
Profile
鉄 多加志
Tetsu Takashi
1965年(昭和40年)生まれ 静岡市出身
東海大学海洋学部 海洋生物学科准教授

ダイビング歴41年、潜水時間約1万3800時間。
国内70数カ所、海外20数カ所を含む約100カ所で潜っている。「ひとつの知識と経験が、同じ場所の同じ風景、生物をもっと魅力的にする」というモットーの下、同じ場所に潜って観察を続けるダイバーで、潜水歴の約8割は三保真崎。大学でも、「好奇心を持ち続けることで、同じ風景や生きものが同じように見えることはない」という観点で履修学生を指導している。
専門は潜水法で「浅海域での長時間潜水時におけるEANガス使用の研究」、「水中遺跡(沈船)潜水調査における安全対策の検討」「水中遺跡(沈没船)調査における安全な潜水方法の研究」(いずれも東海大学海洋研究所研究報告)をはじめ研究論文は多数。
主な著書(共著)に、オーシャンエクササイズ、駿河湾学、海洋考古学入門(いずれも東海大学出版)、THE DEEP SEA(静岡新聞社)、図版 世界の水中遺跡(グラフィック社)などがある。



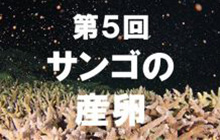






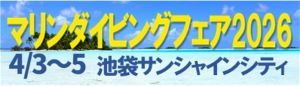


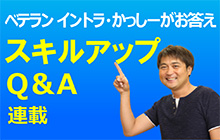

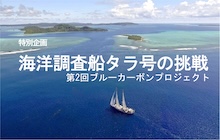
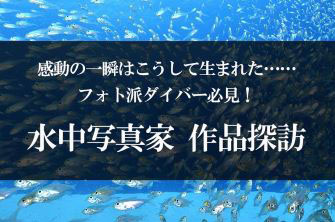






 マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!
マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!