連載
ダイビング博士 山崎先生のダイビングを科学する!
第11回「“浮力”と水深のグラフ」

ダイビング初心者の中には、なかなか上手にならない、と悩む方も多いですよね。一方で熟練インストラクターでも、自分ではできるけど人に理由をうまく説明できない、といった話も…
この連載「ダイビング博士 山崎先生のダイビングを科学する!」ではダイビングの悩みや疑問を科学的にわかりやすく解説します。第11回のテーマはずばり「“浮力”と水深のグラフ」。科学的にダイビングを理解することで、スキルアップを目指しましょう!
※2025年7月の情報です
こんにちは! 目指すは「ダイビング博士」の山崎詩郎です。普段は東京科学大学(旧東京工業大学)理学院物理学系の助教として物理学の研究と教育を行っています。そのかたわらで、科学を誰にでもわかりやすく伝える科学コミュニケーターとして、TV出演や映画の科学監修を多数務めています。

先日、日本テレビの『THE突破ファイル』という番組で科学監修を担当しました。そのときに、なんとダイビングの知識が役に立ちましたので、どんなネタだったか少し紹介しましょう。プールで浮き輪を使ったことはありますか?浮き輪は楽しいものですが、少し面倒なのは使い終わった浮き輪をギューッと押しつぶす作業で、普通に手でつぶすとだいたい数分もかかってしまいます。ところが、視聴者から寄せられたとある簡単な方法を使うと、2倍も速く押しつぶすことができるというのです。はたしてどんな方法でしょうか? その方法とは、浮き輪をプールに少しだけ沈めながら手で縮めるというものでした。私のほうでその原理を科学的に解明してお墨付きを与え、番組では「水圧のおかげ」と一言だけ紹介しました。でも実は、背景にある科学は意外に複雑なものだったんです。ダイビングで水圧に関する余計な知識を得てしまっていたばかりに、、、単純に考えると2倍も速いというのは少し変だなと気が付いてしまったんです。どういうことでしょうか?

我々の身の回りの空気は1気圧です。浮き輪をプールに10cm程度少し沈めると水圧はどれくらい増えるでしょうか? 果たして2倍になるでしょうか? 水圧は10mで1気圧増えることを思い出してください。すると10cm(←メートルではなく!)ではわずか1.01気圧、たったの1%しか増えません。それではなぜ空気を抜くのが2倍も速くなったのでしょうか? ここでは説明しませんが、もしわかった人がいたらぜひご連絡ください。ここで言いたかったことは、プールで浮き輪を速く縮める方法ではありません。プールや浮き輪などのとても身近なところにも圧力や水圧の科学が隠れており、それを知ることで生活の役に立つということです。ダイビングにも数多く圧力や水圧の科学が隠されており、それを知ることでスキルアップに役立ちます。
第11回となる今回は、前回導いた近似版の“浮力”と水深の関係を、具体的に計算してグラフを作ってみましょう。いよいよ“浮力”の形が見えてきます。
近似版の“浮力”と水深の関係
この連載の第10回となる前回は「近似版の“浮力”と水深の関係」を数式で表現しました。復習すると以下のようになります。

ダイバーの言う“浮力”は、最初の項である気体の浮力から、2つ目の項であるウエイトの重力を引き算したものということです。もとから中性浮力に近い状態になっている人間や機材のことは忘れて、極端に軽い気体と、極端に重たいウエイトのことだけ考えればだいたいOKという幸運な結果でした。
式をより簡単にしてみよう
では、この式がどのような姿をしているのか、もう少し具体的に計算してみましょう。この連載の第7回では、気体の体積と水深の関係を、より具体的な式に置き換えました。復習すると以下のようになります。

それでは、この式の置き換えを近似版の“浮力”と水深の関係の分数のところに代入してみましょう。すると以下のような式になります。

だいぶ簡単な形になってきましたね。ここで、液体の密度ρを単純に淡水の1g/cm³として、さらにわかりやすくするために全体を重力の強さgで割ってみましょう。すると、以下のようになります。

最初の“浮力”F/gをはじめ、1項目の気体の浮力も、2項目のウエイトの重力も、力ではなく重さの単位で測った式になっています。力より重さのほうがずっと馴染みやすいからそうしました。そういう意味でこの式は、“浮力”と水深の関係の重さ版と言えます。ついに、“浮力”Fがウエイトの重さmwと、1気圧での気体の体積Vg0と、水深dの3つのみで表すことができました。これら3つは実際のダイビングで実測できてしまうものです。つまり、ついに“浮力”が計算できる準備が整いました。
“浮力”を計算してみよう

では、実際のダイビングの状況を例に、“浮力”を計算してみましょう。ウエイトの重さmwは、きりのいい5kgにしてみましょう。厄介なのは1気圧での気体の体積Vg0です。BCDのバッグの体積は最大で大雑把に10Lなので、ここでは半分程度の5L吸気したと考えてみましょう。ウェットスーツの体積は数Lですので、ここでは大雑把に含まれる気泡は5Lと考えてみましょう。すると、1気圧での気体の体積はきりのいい10Lになります。これらの値を使うと、水深dでの“浮力”を計算する式は以下のようになります。

とても簡単な式になりましたね。この式を、各水深で“浮力”を計算した表が以下となります。ただし、水深はマイナスで測ることにご注意ください。

水深が-10mのときにちょうど“浮力”がゼロの中性浮力になることがわかります。また、それより浅いと浮力は+1.7kgや+5.0kgと急激にプラス“浮力”になり、急浮上しやすいことがわかります。逆に、それより深いと浮力は-1.0kgや-1.7kgと穏やかにマイナス“浮力”になり、水深が深いところでのダイビングは比較的安定していることがわかります。
そして、この式をグラフにしたものが以下となります。

横軸は水深をメートルで測ったd (m)、縦軸は“浮力”をkgで測ったF/g (kg)です。ここから、水深が-10mのときにちょうど“浮力”がゼロの中性浮力になることがわかります。そして、中性浮力になるのは水深がちょうどピッタリ-10mの一瞬しかないこともグラフから一目瞭然です。少しでも水深が-10mより浅くなれば、プラス“浮力”になり、ますます水深が浅くなり、さらにプラス“浮力”になるという悪循環におちいります。これが急浮上です。逆に、少しでも水深が-10mより深くなれば、マイナス“浮力”になり、ますます水深が深くなり、さらにマイナス“浮力”になるという悪循環におちいります。これは潜水墜落と呼ばれています。この連載の第4回は、「中性浮力は不可能」という爆弾発言で締めくくりました。今回まで、“浮力”と水深の関係を定式化し、ついにグラフ化することができましたが、残念ながら結論は変わらなかったんです。もう一度言いましょう。「中性浮力は不可能」なんです…
まとめ

第11回となる今回は、“浮力”と水深の関係をより簡単にし、ダイビングの状況にあった具体的な値を計算しました。また、“浮力”と水深の関係を表やグラフにしました。そして、「中性浮力は不可能」であることを改めて説明しました。…じゃあいったいどうしろと言うのでしょうか…この連載は何だったのでしょうか…安心してください! 不可能を可能にする方法があるんです。いきなりその方法を紹介して解決してはつまらないので、次回は「中性浮力は不可能」という逆境をもう少し楽しんでみましょう。世界初(?!)の“浮力”ポテンシャルという新しい視点のグラフが登場します。
この連載では、ダイビングの科学に関する素朴な疑問を大募集しています。初心者の方からインストラクターの方まで、ぜひ質問を編集部までお寄せください。皆様の質問が記事に採用されるかもしれません。
≫質問・疑問はこちら!
※お問い合わせ内容に「山崎先生に質問!」と記載してください
物理学者
山崎 詩郎 (YAMAZAKI, Shiro)
東京大学大学院理学系研究科物理学専攻にて博士(理学)を取得後、日本物理学会若手奨励賞を受賞、東京科学大学理学院物理学系助教に至る。科学コミュニケーターとしてTVや映画の監修や出演多数、特に講談社ブルーバックス『独楽の科学』を著した「コマ博士」として知られている。SF映画『インターステラー』の解説会を100回実施し、SF映画『TENET テネット』の字幕科学監修、『クリストファー・ノーランの映画術』(玄光社)の監修、『オッペンハイマー』(早川書房)の監訳、『片思い世界』の科学監修を務める「SF博士」でもある。2022年秋に始めたダイビングに完全にハマり、インストラクターを目指して現在ダイブマスター講習中。次の目標は「ダイビング博士」。









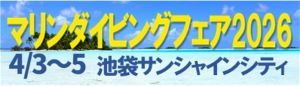


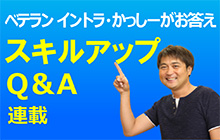

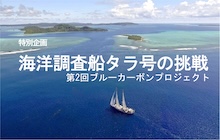
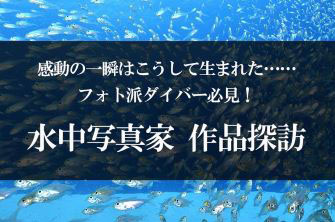






 マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!
マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!