連載
ダイビング博士 山崎先生のダイビングを科学する!
第12回「世界初!? “浮力”ポテンシャル」

ダイビング初心者の中には、なかなか上手にならない、と悩む方も多いですよね。一方で熟練インストラクターでも、自分ではできるけど人に理由をうまく説明できない、といった話も…
この連載「ダイビング博士 山崎先生のダイビングを科学する!」ではダイビングの悩みや疑問を科学的にわかりやすく解説します。第12回のテーマはずばり「世界初!? “浮力”ポテンシャル」。科学的にダイビングを理解することで、スキルアップを目指しましょう!
※2025年8月の情報です
こんにちは! 目指すは「ダイビング博士」の山崎詩郎です。普段は東京科学大学(旧東京工業大学)理学院物理学系の助教として物理学の研究と教育を行っています。そのかたわらで、科学を誰にでもわかりやすく伝える科学コミュニケーターとして、TV出演や映画の科学監修を多数務めています。

突然ですが、万博にはもういかれましたか? 私はこの3か月間で13回も万博に行き、9割以上のパビリオンを制覇してきました。ダイバー視点で万博に参加することで、とある意外なことに気がついたんです。万博のテーマはいのちとみらいですが、裏テーマはなんと海…! 海や水を前面に押し出したパビリオンやイベントが明らかに多かったんです。例えば、撥水のインスタレーションや半球面の海の映像が美しかった「ブルーオーシャンドーム」。中東の砂漠の国かと思いきや、真珠産業や伝統的な素潜りの展示をした「カタール」や「バーレーン」。球面ディスプレイに黒潮、巨大ディスプレイにクラゲや魚群を映し出した「スペイン」。複数のディスプレイで架空の海亀やクジラを写しながらどんどん深海に潜降する「オーストラリア」。海が形づくる国と宣言し巨大スクリーンで魚影に包まれる「ポルトガル」。そして、噴水とレーザーがこの世のものとは思えないほど美しいメインイベントの「アオと夜の虹のパレード」。よく考えれば、海辺での開催ですし、そもそも日本は海に囲まれた国。各国のパビリオンが寄り添ってくれたのかもしれませんね。今回の万博、ダイバーにこそお勧めです。
第12回となる今回は、前々回導いた近似版の“浮力”と水深の関係を、さらに計算を進めて“浮力”ポテンシャルなるものを導いてみましょう。“浮力”の真の姿が見える一歩手前まで進みます。
近似版の“浮力”と水深の関係
この連載の第10回となる前々回は「近似版の“浮力”と水深の関係」を数式で表現しました。復習すると以下のようになります。

大切な式なので四角で囲っておきました。ダイバーの言う“浮力”は、最初の項である気体の浮力から、2つ目の項であるウエイトの重力を引き算したものということです。もとから中性浮力に近い状態になっている人間や機材のことは忘れて、極端に軽い気体と、極端に重たいウエイトのことだけ考えればだいたいOKという幸運な結果でした。
この連載の第11回となる前回は、この式をより具体的に計算し、数字や表やグラフにしていきました。そして「中性浮力は不可能」という衝撃的な結論にたどり着きました。中性浮力になるのは厳密にある水深になる一瞬だけです。ほんの1mmでも水深が浅くなれば、プラス“浮力”になり、ますます水深が浅くなり、さらにプラス“浮力”になるという悪循環におちいります。これが急浮上です。逆に、ほんの1mmでも水深が深くなれば、マイナス“浮力”になり、ますます水深が深くなり、さらにマイナス“浮力”になるという悪循環におちいります。これは潜水墜落と呼ばれています。

このような状況は、次の状況と似ています。鉛筆をとがっているほうを下にして机の上に立ててみましょう。すると、ほんの少しでも右に傾くとどんどん右に傾いて倒れてしまいます。逆に、ほんの少しでも左に傾くとどんどん左に傾いて倒れてしまいます。鉛筆をとがっているほうを下にして机の上に立てることなどできません。中性浮力も鉛筆も物理的には同じ状況にあり、専門的には「不安定な解」と呼ばれています。要は、計算上は不可能ではないが、現実的には不可能ということです。
ダイビングで「中性浮力が不可能」なんて言われても困ってしまいますよね。でも、不可能を可能にする方法をあせって考える前に、急がば回れ。もう少し「中性浮力は不可能」という状況を詳しく見てみましょう。その前準備として先ほどの式の分数の部分をP0で割り算しておきます。すると以下のようになります。

位置エネルギーってなんだろう?

いったんダイビングから離れて、ビーチに転がっているウエイトで軽いトレーニング遊びをしてみましょう。重さ2kgのウエイトが、ビーチに置いてあるとします。そのウエイトを50cm持ち上げてみましょう。その結果、体はほんの少しだけ疲れ、ほんの少しエネルギーを使うと思います。では、そのウエイトを手からパッと放して、50cmの高さからビーチに落としてみましょう。その結果、ビーチに衝突してほんの少しへこんでしまうと思います。
では、今度は同じ重さ2kgのウエイトを、さきほどより高い100cm持ち上げてみましょう。その結果、体はさきほどより疲れ、さきほどよりエネルギーを使うと思います。では、そのウエイトを手からパッと放して、100cmの高さからビーチに落としてみましょう。その結果、ビーチに衝突してさきほどよりへこんでしまうと思います。
繰り返しになりますが、今度は同じ重さ2kgのウエイトを、さらに高い150cm持ち上げてみましょう。その結果、体はさらに疲れ、さらにエネルギーを使うと思います。では、そのウエイトを手からパッと放して、150cmの高さからビーチに落としてみましょう。その結果、ビーチに衝突してさらにへこんでしまうと思います。

このように、重たいものを高く持ち上げるのはエネルギーが必要で、また高いところから落とすとエネルギーが発生します。まるで、高さにエネルギーが蓄えられているようです。物理的には、下向き働いている重力に逆らって物体を上向きに動かした時に、物体にはエネルギーが溜まると考えます。このようなエネルギーは位置エネルギーと呼ばれています。力と移動距離を掛け算すると位置エネルギーを計算できます。
今回の重力の場合はどこでも一定の力なので単純な掛け算で済みました。ところが、世の中には場所によって連続的に大きさが変化する力のほうが普通です。そのような場合は、掛け算を積分に置き換えれば大丈夫なんです。つまり、力を位置で積分すると位置エネルギーになります。
位置エネルギーのようなものを、潜在的なエネルギーという意味でポテンシャルエネルギー、もしくは略してポテンシャルと呼ばれています。「あの人の成績は良くないが、これから急に成長するポテンシャルがあると思う」などと、潜在的な力を評価するのにも日常的に使いますよね。ポテンシャルという言葉を使えば、力を位置で積分するとポテンシャルになるといえます。
“浮力”を積分して“浮力”ポテンシャル

ついにこの連載で最も難しい部分に到達してしまいました…高校数学で悪名名高き微分積分の登場です…数式の計算がわからなくても全く心配ありません。数式は一種のアートだと思って、その全くわからない感じ、なんとなくすごそうな計算をしている感じをぜひ楽しんでください。ダイビングで積分です…かんかカッコいいじゃないですか…! 一方で、もちろん微分積分がわかる方は計算を追ってみてください。実は教科書レベルの基本的な計算で決して難しくありません。
先ほど、力を位置で積分するとポテンシャルになると説明しました。これをダイビングに置き換えてみましょう。ここで、力を“浮力”、位置を水深、ポテンシャルをその名も“浮力”ポテンシャルに置き換えると、“浮力”を水深で積分すると“浮力”ポテンシャルになると言い換えることができます。それを表現したのが次の数式です。

ここで、 “浮力”は今まで通り力を表すForceのF、“浮力”ポテンシャルは慣習でUと表しています。そしてアルファベットのSを縦にニョロッと伸ばしたような記号とddは、水深dで積分することを表しています。マイナスは力に逆らうとポテンシャルが溜まることを意味しています。
積分してみよう
それではこの式に、最初の“浮力”Fを代入して積分してみましょう。安心してください。今回使う積分は定数の積分と逆数の積分のたった2種類だけで、次のように公式としてまとめておきました。定数aをxで積分すると一次の式ax、逆数1/xをxで積分すると対数ln(x)というものになります。

“浮力”Fの2項目のウエイトの重力は水深dと関係ない定数です。ですので1つ目の定数の積分公式を使いましょう。単にdをかければよいだけです。“浮力”Fの1項目の気体の浮力は水深dが分母に入っている厄介な項です。ですが、2つ目の逆数の積分公式、または3つ目のその派生を用いましょう。分母を対数lnの中に入れて、係数で割るだけです。このようにして“浮力”ポテンシャルを計算すると以下のようになります。

これを整理すると、世界初(!?)の“浮力”ポテンシャルが得られます。大切な式なので四角で囲っておきました。

Uは“浮力”ポテンシャル、1項目は気体の浮力のポテンシャル、2項目はウエイトの重力のポテンシャルです。連載1周年にしてついに一つのゴールに到達しました。
まとめ

第12回となる今回は、近似版の“浮力”と水深の関係を積分することで、世界初(!?)の“浮力”ポテンシャルを導出しました。少し難しかったですが、大切なのは数式ではなく意味を感じることですので安心してください。では、この“浮力”ポテンシャルはどのような形をしているのでしょうか? 次回は“浮力”ポテンシャルのグラフを描き、ダイバーがいったいどのようなポテンシャルの中をただよっているのかを説明します。「中性浮力は不可能」と言っていた意味がグラフから一目瞭然でわかります。
この連載では、ダイビングの科学に関する素朴な疑問を大募集しています。初心者の方からインストラクターの方まで、ぜひ質問を編集部までお寄せください。皆様の質問が記事に採用されるかもしれません。
≫質問・疑問はこちら!
※お問い合わせ内容に「山崎先生に質問!」と記載してください
物理学者
山崎 詩郎 (YAMAZAKI, Shiro)
東京大学大学院理学系研究科物理学専攻にて博士(理学)を取得後、日本物理学会若手奨励賞を受賞、東京科学大学理学院物理学系助教に至る。科学コミュニケーターとしてTVや映画の監修や出演多数、特に講談社ブルーバックス『独楽の科学』を著した「コマ博士」として知られている。SF映画『インターステラー』の解説会を100回実施し、SF映画『TENET テネット』の字幕科学監修、『クリストファー・ノーランの映画術』(玄光社)の監修、『オッペンハイマー』(早川書房)の監訳、『片思い世界』の科学監修を務める「SF博士」でもある。2022年秋に始めたダイビングに完全にハマり、インストラクターを目指して現在ダイブマスター講習中。次の目標は「ダイビング博士」。









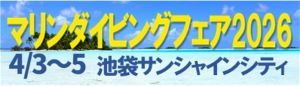


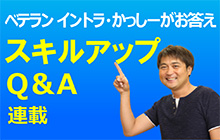

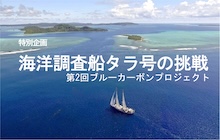
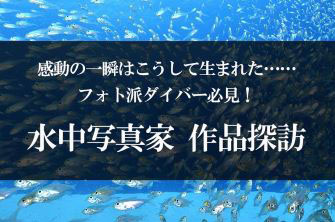






 マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!
マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!