連載
ダイビング博士 山崎先生のダイビングを科学する!
第13回「“浮力”の真の姿」
“浮力”ポテンシャルのグラフは山!

ダイビング初心者の中には、なかなか上手にならない、と悩む方も多いですよね。一方で熟練インストラクターでも、自分ではできるけど人に理由をうまく説明できない、といった話も…
この連載「ダイビング博士 山崎先生のダイビングを科学する!」ではダイビングの悩みや疑問を科学的にわかりやすく解説します。第13回のテーマはずばり「“浮力”の真の姿」。科学的にダイビングを理解することで、スキルアップを目指しましょう!
※2025年9月の情報です
こんにちは! 目指すは「ダイビング博士」の山崎詩郎です。東京科学大学(旧東京工業大学)理学院物理学系にて物理学の研究と教育を行い、TVでの科学解説や映画の科学監修を多数担当しています。
突然ですが、「印旛沼ダンボールイカダCUP」という競技大会をご存知でしょうか? この大会は、流れのほとんどない千葉県の印旛沼にて、ダンボールとガムテープのみを使って船をつくり、150mレースでタイムを競うというものです。TBSテレビ「有吉ジャポンII ジロジロ有吉」という番組でこの大会に挑戦する企画が立ち上がりました。この連載のおかげか、なんと私が「浮力」の専門家として出演することになり、船の設計から製造までを一手に引き受けることになったのです…! この連載で登場した「世界初!?の”浮力”ポテンシャル」もTVでバッチリうつりました。ダイビング関係(?)でTV出演するのは初めてだったのでうれしい出来事でした。

船のこぎ手はいまをときめく芸人の高木ひとみ〇さん。最近ダイエットに成功し、現在の体重は70kgです。与えられたダンボールは幅1mで長さ2m、これをそのまま船底に使います。さて、ここでクイズです。船の側壁をどれくらいの高さにしたらよいでしょうか? これを計算してわかりやすく科学解説するのが私の最初の収録でした。

船の浮力は押しのけた水の重さと等しくなりますので、幅1m×長さ2m×高さ?m×水の密度1000 kg/m3になります。これがちょうど体重70kgと等しくなればよいので、計算すると高さは70÷1000÷2=3.5cmとなりました。意外と低くて大丈夫なんです。とはいえ、レース本番では揺れたり波があったり勢いよくこいだりするので、かなり余裕をもって10倍ほど高い側壁でガッチリ固めました。
これらの浮力の計算を元に、船を強固にするダンボールのトラス構造や、船を防水にするガムテープの網代張りなどを駆使して、40時間もかけて船を製造しました。そして本番に挑んだ結果…なんと「印旛沼ダンボールイカダCUP」で優勝することができました…! 念願の初優勝にこぎ手の高木ひとみ○さんも涙、これにはさすがにスタジオの有吉さんや後藤真希さんや銀シャリも大喜びでした。このように、浮力ひとつでも極めれば大会で優勝する大きな原動力になります。ダイビングでも同じだと思います。たかが浮力、されど浮力。浮力ひとつでも極めればダイビング上達の大きな原動力になります。
第13回となる今回は、前回導いた“浮力”ポテンシャルを具体的に計算し、“浮力”の真の姿を見てみましょう。中性浮力は不可能と言った真意が一目でわかります。
“浮力”ポテンシャル/数式版
この連載の第12回となる前回は、“浮力”を水深で積分して世界初(?!)の“浮力”ポテンシャルなるものを計算し数式で表現しました。復習すると以下のようになります。

大切な式なので四角で囲っておきました。Uは“浮力”ポテンシャル、1項目はBCDやスーツなどの気体の浮力のポテンシャル、2項目はウエイトの重力のポテンシャルです。とても難しいですよね。でも安心してください。数式は一種のアート作品だと思って眺めていただければ大丈夫です。
“浮力”ポテンシャル/数字版
では、この数式に具体的な数字を代入して、この数式のグラフの形を求めてみましょう。この数式の目的は、青文字の水深dから、赤文字の“浮力”ポテンシャルUを計算することです。そのためには、それ以外の数である、P0、Vg0、ρ、mw、gの5つの具体的な値を知る必要があります。幸い、ダイビングにおいてそれらの値は全てわかっています。それをまとめたのが次の表です。

P0は大気圧。高所ダイビングでもない限り、通常の海でのダイビングでは1気圧です。Vg0はBCDとスーツの気体の体積。今回は10リットルとしておきます。ρは水の密度。海水でも真水と同じ1と考えて大丈夫です。mwはウエイトの重さ。今回は5kgとしておきます。gは重力の強さ。地球外の他の惑星でダイビングでもしない限り、値はいつも同じなので気にしなくて大丈夫です。これら5つの具体的な値を“浮力”ポテンシャルの数式に代入したのが次の式です。

だいぶスッキリしましたね。高校数学で習う自然対数lnの計算は残っていますが、それ以外は足し算、引き算、掛け算だけの小学生でもできる数式になりました。これでついに、青文字の水深dから、赤文字の“浮力”ポテンシャルUを計算することができます。
“浮力”ポテンシャル/グラフ版
ついに、世界初(!?)の“浮力”ポテンシャルのグラフを目の当たりにする瞬間が来ました。先ほどの数式をグラフにしたものが次の図です。

横軸は水深。一番右側の0mが水面で、左側に行くほどマイナスになり深く潜降していくことを意味します。縦軸は“浮力”ポテンシャルで、その値は赤い太線で描かれています。“浮力”ポテンシャルの形はなんと山のような形をしていることがわかります。 “浮力”ポテンシャルは、水深0mでは小さく、潜降するにしたがって急に大きくなり、水深-10mで最大になります。さらに潜降するにしたがって穏やかに小さくなり、そのまま小さくなり続けます。
山の頂上にビー玉を置くのは不可能
このグラフに物理的な意味を書き加えたのが次の図です。

“浮力”ポテンシャルの意味はずばり山にビー玉。赤い太線の山の上にビー玉を置いたらどのように転がるかが、実際のダイビングでの動きを教えてくれます。山の右側の斜面にビー玉を置いたら、さらに右側に転がり続けます。つまり、赤い矢印で示したように急浮上します。山の左側の斜面にビー玉を置いたら、さらに左側に転がり続けます。つまり、赤い矢印で示したように潜水墜落します。そして、本当に完全に完璧に原子一個分のズレもなく山の頂上にビー玉を置いたときのみ、どちらにも転がらずに止まります。これが青い丸で示した中性浮力です。
しかし、本当に完全に完璧に原子一個分のズレもなく山の頂上にビー玉を置くことなどできるのでしょうか?それは不可能です。前回の例えを借りれば、鉛筆をとがったほうを下にして机の上に立てるようなものです。このような状況は「不安定な解」と言われています。要は、計算上の概念で、実際には実現できないということです。つまり、中性浮力は不可能なんです。
まとめ

第13回となる今回は、世界初(!?)の“浮力”ポテンシャルを具体的に計算し、そのグラフを描きました。そして、それが山のような形をしており、山の頂上にビー玉を置くことはできないことから、中性浮力が不可能であることを説明しました。とはいっても、ダイビングの基本的なスキルである中性浮力が不可能だと言われても困ってしまいますよね。中性浮力を現実的に可能にする方法を探る前に、次回は中性浮力になる理想的な水深、「中性浮力水深」という新しい概念を紹介します。
この連載では、ダイビングの科学に関する素朴な疑問を大募集しています。初心者の方からインストラクターの方まで、ぜひ質問を編集部までお寄せください。皆様の質問が記事に採用されるかもしれません。
≫質問・疑問はこちら!
※お問い合わせ内容に「山崎先生に質問!」と記載してください
物理学者
山崎 詩郎 (YAMAZAKI, Shiro)
東京大学大学院理学系研究科物理学専攻にて博士(理学)を取得後、日本物理学会若手奨励賞を受賞、東京科学大学理学院物理学系助教に至る。科学コミュニケーターとしてTVや映画の監修や出演多数、特に講談社ブルーバックス『独楽の科学』を著した「コマ博士」として知られている。SF映画『インターステラー』の解説会を100回実施し、SF映画『TENET テネット』の字幕科学監修、『クリストファー・ノーランの映画術』(玄光社)の監修、『オッペンハイマー』(早川書房)の監訳、『片思い世界』の科学監修を務める「SF博士」でもある。2022年秋に始めたダイビングに完全にハマり、インストラクターを目指して現在ダイブマスター講習中。次の目標は「ダイビング博士」。










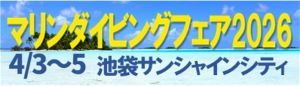


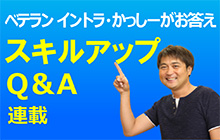

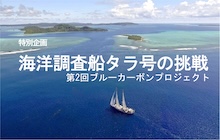
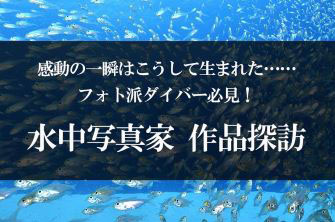






 マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!
マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!