連載
ダイビング博士 山崎先生のダイビングを科学する!
第14回「中性浮力水深」とは

ダイビング初心者の中には、なかなか上手にならない、と悩む方も多いですよね。一方で熟練インストラクターでも、自分ではできるけど人に理由をうまく説明できない、といった話も…
この連載「ダイビング博士 山崎先生のダイビングを科学する!」ではダイビングの悩みや疑問を科学的にわかりやすく解説します。第14回のテーマはずばり「“中性浮力水深”とは」。科学的にダイビングを理解することで、スキルアップを目指しましょう!
※2025年10月の情報です
こんにちは! 目指すは「ダイビング博士」の山崎詩郎です。東京科学大学(旧東京工業大学)理学院物理学系にて物理学の研究と教育を行い、TVでの科学解説や映画の科学監修を多数担当しています。
第14回となる今回は、“浮力”と水深の関係から、中性浮力になる唯一の水深「中性浮力水深」という新しい考え方を導きます。「中性浮力水深」を意識することは中性浮力をマスターするための大きな助けになります。
“浮力”と水深の関係
この連載の第10回では、“浮力”と水深の関係を数式で表現しました。復習すると以下のようになります。

大切な式なので四角で囲っておきました。赤い字のFは“浮力”、青い字のdは水深です。1項目はBCDやスーツなどの気体の浮力、2項目はウエイトの重力です。とても難しいですよね。でも安心してください。数式は一種のアート作品だと思って眺めていただければ大丈夫です。大切なことは、青い字の水深dと赤い字の“浮力”Fは密接に結びついているということを感じ取ることです。青い字の水深dが決まれば赤い字の“浮力” Fも唯一ひとつに決まります。逆に、赤い字の“浮力” Fがある値になるような青い字の水深dも唯一ひとつに決まります。青い字の水深dと赤い字の“浮力”Fは一対一に関係づけられているのです。
中性浮力になる唯一の水深「中性浮力水深」
では、“浮力” Fがちょうどゼロになる、つまり中性浮力になるような唯一の特別な水深dを計算してみましょう。先ほどの式で赤い字の“浮力” Fにゼロを代入したのが以下の式になります。

この式を変形して青い字の水深dを求めていきましょう。この式は一見複雑ですが、よく見ると小学校の時に習った足し算引き算かけ算わり算しか使っていませんので落ち着いてください。水深dを求める途中計算を掲載したのが以下の式です。

最後に水深dを求めたのが以下の式です。

大切な式なので四角で囲っておきました。これが、中性浮力になる唯一の特別な水深を示しており、「中性浮力水深」dnと名付けます。dの右下のnは中性を意味する英語neutral の頭文字です。
「中性浮力水深」が存在する条件
この式でとっても気になるところがあるんです。それはカッコの中の引き算です。引く数と引かれる数の大小関係によって、正になったり負になったりします。ところが、中性浮力水深dnは水面より必ず下になければならない、すなわち負の値dn<0でなければなりません。ということは、カッコの中の引き算も負の値でなければなりません。その条件を数式で表したのが次の式です。

この式を少しだけ計算したのが以下の式です。

大切な式なので四角で囲っておきました。これが「中性浮力水深」dnの存在する条件です。式の左側はウエイトの重さmwをBCDやスーツの気体の体積Vg0で割ったもの、つまり器材の密度です。式の右側は水の密度ρです。不等号の意味は、器材の密度が水の密度よりも小さくなければならないということです。もしそうでなければ、BCDに吸気した状態でも水の密度よりも重く沈んでしまいます。そんなようでは、潜降した後に水中で中性浮力になることは絶対にありません。水面で沈むなら水中で中性浮力になることはない。これは、当たり前なことですよね。でも、この当たり前のことがしっかり式に含まれていたということは、この式は信頼して大丈夫そうです。
「中性浮力水深」はどう変化する?
それでは最後に、実用的なことを考えてみましょう。中性浮力になる唯一の水深である「中性浮力水深」はどのような条件で変化するのでしょうか?もう一度「中性浮力水深」の式を見てみましょう。先に結果をまとめると、以下の表のようになります。

まず、BCDやスーツなどの気体の体積Vg0が大きいほど、カッコの中のマイナスが大きくなり、dnはマイナス方向に大きくなり、「中性浮力水深」は深くなります。実際のダイビングで、水深が深いほどBCDに空気を入れるのはそのためです。次に、ウエイトの重さmwが重いほど、カッコの中のマイナスが小さくなり、dnはマイナスのままゼロに近づき、「中性浮力水深」は浅くなります。実際のダイビングで、オーバーウエイトだと浅場でしか中性浮力にならなくなるのはそのためです。

また、普段は気にしませんが、水の密度ρが高いほど、カッコの中のプラスが小さくなり、dnはマイナス方向に大きくなり、「中性浮力水深」は深くなります。実際のダイビングでは、淡水より海水のほうが水の密度が高く、浮力が大きくなり、同じウエイトで潜ればより深いところで中性浮力になります。さらに、大気圧P0が大きいと、「中性浮力水深」は深くなります。実は、高所ダイビングでは大気圧が低い分だけ水面でBCDが余計に膨らみ「中性浮力水深」が少し浅くなっているんです。もしかすると、このことを世界で初めて気が付いたダイバーは私かもしれません…なお、空気の無い月ではBCDを用いたダイビングは困難になります。水面の上下で気圧の変化が激しすぎて、「中性浮力水深」がほぼ水面になってしまうからです。最後に、重力の強さgが大きいと、gは分母に入っているので、「中性浮力水深」は浅くなります。重力が強いと浮力も強くなるので、「中性浮力水深」も浅くなるんです。もし、地球外ダイビングをする機会があったらこのことを思い出してください。
まとめ

第14回となる今回は、“浮力”と水深の関係から、“浮力”がゼロの中性浮力になる水深である「中性浮力水深」という概念を導入しました。そして、BCDやスーツの気体の体積が大きいほど、「中性浮力水深」が深く、ウエイトの重さが重いほど、「中性浮力水深」が浅いことがわかりました。次回は、「中性浮力水深」がどのように変化するか、表やグラフで具体的に見ていきます。「中性浮力水深」を意識することは中性浮力をマスターするための大きな助けになります。中性浮力は “とる”だけではなく、「中性浮力水深」に“行く”こともできるのです。
この連載では、ダイビングの科学に関する素朴な疑問を大募集しています。初心者の方からインストラクターの方まで、ぜひ質問を編集部までお寄せください。皆様の質問が記事に採用されるかもしれません。
≫質問・疑問はこちら!
※お問い合わせ内容に「山崎先生に質問!」と記載してください
物理学者
山崎 詩郎 (YAMAZAKI, Shiro)
東京大学大学院理学系研究科物理学専攻にて博士(理学)を取得後、日本物理学会若手奨励賞を受賞、東京科学大学理学院物理学系助教に至る。科学コミュニケーターとしてTVや映画の監修や出演多数、特に講談社ブルーバックス『独楽の科学』を著した「コマ博士」として知られている。SF映画『インターステラー』の解説会を100回実施し、SF映画『TENET テネット』の字幕科学監修、『クリストファー・ノーランの映画術』(玄光社)の監修、『オッペンハイマー』(早川書房)の監訳、『片思い世界』の科学監修を務める「SF博士」でもある。2022年秋に始めたダイビングに完全にハマり、インストラクターを目指して現在ダイブマスター講習中。次の目標は「ダイビング博士」。









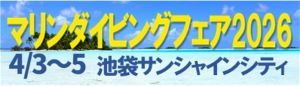


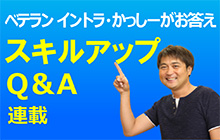

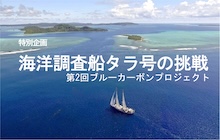
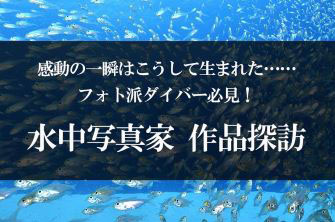






 マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!
マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!