ダイバーなら知っておきたいサンゴのこと
第2回:サンゴの種類

沖縄の島々では5~6月、九州・四国や紀伊半島では7~8月、サンゴの産卵の神秘的な様子が話題となりますが、サンゴって何でしょう?
サンゴやサンゴ礁(※)が地球の環境を守る大事な存在だということは今や小中学校でも学ぶのでご存じの方も多いでしょう。ダイバーなら知っておきたいサンゴのことを6回連載でお届けします。
サンゴとサンゴ礁の違いは、簡単いうと生物か地形かの違いです。サンゴ礁は主に造礁サンゴが集まって積み重なり、形成されたものです。
世界にサンゴは何種ある?

真っ赤なイソバナと周りには枝状のサンゴなどが見られる
撮影地/西表島
Photo by Marine Photo Library
世界には800種以上のサンゴが生息
たくさんのサンゴの種類が見られるダイビングスポットもある
Movie by Yukari Goto
サンゴといっても、前回紹介したように造礁サンゴと非造礁サンゴがありますが、種類でいえば世界には18科、約120属、800種以上のサンゴが生息しているといわれています(造礁サンゴだけで約1300種、ソフトコーラルが約1600種という説もあります)。日本に生息しているサンゴはそのうちの約300種、特に世界でもサンゴ礁の美しさ、種類の多さで有名な沖縄の海には約200種ものサンゴが生息しています。素晴らしいことですね。 それにしてもサンゴにそんなに種類があることも驚きではないですか?
ハードコーラルとソフトコーラル
造礁サンゴのほとんどがハードコーラル

いかにも硬そうな骨格を持つサンゴたち 撮影地/西表島「鳩間島北」
Photo by Marine Photo Library
サンゴの中には強固で綿密な骨格を持つサンゴがあり、これを「ハードコーラル」と呼びます。そしてこのハードコーラルがサンゴ礁を形成する造礁サンゴの大部分を占めています。
ポリプを持つのに骨格らしきものがないソフトコーラル

ウミトサカと呼ばれるこの美しい生き物もサンゴの一種です 撮影地/伊豆半島
Photo by Marine Photo Library
ダイビングで出会って初めて存在を知る人も少なくないと思いますが、ウミトサカやウミアザミなどもサンゴの仲間です。でもハードコーラルと異なり細かい石灰質の骨格(骨片)を体の中にちりばめた状態であることから、軟体となっています。これらを「ソフトコーラル」と呼びます。幹は硬いけれど、木のように枝をいくつも延ばす、鮮やかな色彩で知られるイソバナの仲間もソフトコーラルに入ります。
知っておきたい主なハードコーラル
沖縄・奄美など亜熱帯海域に生息
沖縄の島々や奄美諸島で潜っているとき、息を呑むほど美しいサンゴ礁に出会うことがあります。これらの正体はほとんどがハードコーラル。日本では沖縄や奄美諸島などの亜熱帯海域に、世界でも亜熱帯〜熱帯の海域に主に生息しています。よく見ると、いろいろな種類が共存しています。ここではダイビングでよく見かけるサンゴの仲間(科)を紹介します。
ミドリイシ科

ミドリイシの仲間は特に種類が多い。写真中のサンゴの種類は他の種類である可能性がありますのでご了承ください
Photo by Marine Photo Library
エダサンゴ、テーブルサンゴといわれるサンゴはすべてミドリイシ科のもの。とても種類が多く、見分けがつかないものもとても多いのです。でも、だいたいの名前を知っておくとサンゴ礁を見る目も変わってくるかもしれません。ミドリイシといいながら緑色だけでなく黄色、ピンク色、青色など色彩の幅も広くフォトジェニック。

この大きなテーブルサンゴもミドリイシの仲間(ミドリイシ科)で、直径2m以上になるものも多いクシハダミドリイシ 撮影地/沖縄本島国頭村
Photo by Marine Photo Library
◎その他の主なミドリイシの仲間
エダコモンサンゴ、ノリコモンサンゴ、コエダミドリイシ、ヒメマツミドリイシ、ハイマツミドリイシ、ハナバチミドリイシ、ハナガサミドリイシ、サボテンミドリイシ、アナサンゴなど
ハマサンゴ科

ハマサンゴの中でもとても大きく成長するコブハマサンゴ 撮影地/慶良間諸島阿嘉島
Photo by Yukari Goto

ハマサンゴにも枝状になるものがあります。ユビエダハマサンゴ 撮影地/西表島
Photo by Marine Photo Library
ミドリイシと違ってサンゴの塊にびっしりと1.5mm程度のポリプが並んでいるのが特徴です。色は黄色、黄緑色、淡褐色。
◎その他の主なハマサンゴの仲間
ベニハマサンゴ、フカアナハマサンゴ、スジハマサンゴ、オキナワハマサンゴ、ムレイハマサンゴ、キクメハナガササンゴ、マルアナハナガササンゴなど
サザナミサンゴ科

菊の花のようなポリプがびっしり隙間なく並んでいるのが特徴のキクメイシ 撮影地/ケラマ諸島阿嘉島
Photo by Yukari Goto
半球形、塊状の群体で見た目は大小の石のようですが、表面は菊の花のような円形、楕円形のポリプに覆われていて、たいてい規則的に並んでいるキクメイシ属と、キャベツコーラルといわれるリュウキュウキッカサンゴのようなタイプがあります。色は黄褐色、淡褐色ほか変化に富んでいます。
※生物学上ではキクメイシ科のサンゴもありますが、一般的によく見られるサザナミサンゴ科のキクメイシ属のサンゴを紹介しています。

リュウキュウキッカサンゴの仲間で、キャベツコーラルなどと呼ばれるサンゴ。広大な群体を形成 撮影地/グアム
Photo by Marine Photo Library
◎その他の主なキクメイシの仲間
カメノコキクメイシ、マルカメノコキクメイシ、ヒメウネカメノコキクメイシ、リュウキュウノウサンゴ、ナガレキクメイシ、マルキクメイシ、アラトゲキクメイシ、ダイオウサンゴなど
ハナサンゴ科

アザミサンゴは尖った隔壁が無数に並んでいます。撮影地/ケラマ諸島阿嘉島
Photo by Yukari Goto
ハナサンゴの仲間には、アザミの花のようにトゲトゲした隔壁に囲まれたポリプがびっしりと隙間なく塊状の群体を形成するアザミサンゴの仲間や、イソギンチャクのようなポリプを持つナガレハナサンゴの仲間などがあります。アザミサンゴは大きなものでは直径2m近く育つものもあります。色は変化に富んでいて海に映えるものも多数。
◎その他の主なハナサンゴの仲間
エダアザミサンゴ、オオナガレハナサンゴ、ハナサンゴ、ハナサンゴモドキなど
キサンゴ科

大きなポリプがとても美しいナンヨウキサンゴ 撮影地/西伊豆 田子
Photo by Marine Photo Library
骨格を持つサンゴではあるけれど、造礁サンゴではない珍しいタイプ。太い樹状の群体を結成し、枝上にポリプが収まる夾(きょう)が突出しています。イソギンチャクのようにポリプを開いているときはとても華やか。また、円形のすり鉢状になるサンゴもある。黄色、オレンジ色など色合いも海中に映えるものが多いです。
◎その他の主なキサンゴの仲間
オオスリバチサンゴ、ツツスリバチサンゴ、ヨコミゾスリバチサンゴ、オノミチキサンゴ、イボヤギ、エダイボヤギなど
ヒラフキサンゴ科

大仏サンゴとか、ジャガイモなどと形容されることの多い、コモンシコロサンゴ。大群落になることも 撮影地/ケラマ諸島阿嘉島
Photo by Yukari Goto

全然形が違うけど同じヒラフキサンゴの仲間でセンベイサンゴ 撮影地/慶良間諸島阿嘉島
Photo by Yukari Goto
イシサンゴも相当種類が多いと思ったが、こちらもなかなか多い。ヒラフキサンゴ科のサンゴは、コロニアル型の造礁サンゴで、しばしば巨大な構造を形成します。また層状、葉状、さらに角柱になるものもあります。ということで、“センベイ”だったりコモンシコロサンゴのような“ジャガイモ”だったりするのですね。。
◎その他の主なヒラフキサンゴの仲間
ヒラフキサンゴ、ヨロンキクメイシ、ウスイタセンベイサンゴ、エダセンベイサンゴ、ヒメエダセンベイサンゴ、チヂミセンベイサンゴなど
ハナヤサイサンゴ科

浅瀬のサンゴ礁エリアに多いハナヤサイサンゴの仲間 撮影地/慶良間諸島阿嘉島
Photo by Yukari Goto
造礁サンゴの上によく棲息している、まさに“花野菜”のようなかわいらしいサンゴ。二叉(にさ)分岐を繰り返しながらブロッコリーのように直径10~20cmの塊を形成しています。枝の間にサンゴガニやパンダダルマハゼ、ダンゴハゼなどが棲息していることがあり、ダイバーに人気です。トゲサンゴの仲間やショウガサンゴの仲間もサザナミサンゴ科に含まれています。
◎その他の主なハナヤサイサンゴの仲間
ホソエダハナヤサイサンゴ、ヘラジカハナヤサイサンゴ、ウスイタハナヤサイサンゴ、チリメンハナヤサイサンゴ、イボハダハナヤサイサンゴ、トゲサンゴ、ショウガサンゴ(ヤスリショウガサンゴ)など
クサビライシ科

クサビライシの仲間が海底に大集合! 撮影地/タイ タオ島
Photo by Yukari Goto
時にはイソギンチャクのようなポリプを延ばしている、たわし形や円形の大きくでも数十cmの個体で、海底に点在、もしくは大集合しているクサビライシの仲間もイシではなくサンゴの仲間。ポリプを伸ばしている個体をよく見てみると、エビやカニが共生していることも。
◎主なクサビライシの仲間
トゲクサビライシ、シロユビトケクサビライシ、スジマンジュウイシ、ワレクサビライシ、パラオクサビライシ、キュウリイシなど
アナサンゴモドキの仲間

黄褐色、淡褐色のものが多い。こんな感じの群落をつくっているので触らないようにご注意を 撮影地/慶良間諸島阿嘉島
Photo by Yukari Goto
これまでのイシサンゴの仲間(イシサンゴ目)と異なり、ヒドロサンゴ目に分類されているサンゴです。サンゴ礁の浅海域に生息していて、樹状の群体を形成して広がっているものが多いです。触ると刺されて火傷のような痛さをもたらすため「ファイヤーコーラル」「火炎サンゴ」などと呼ばれています。刺されるとかなり痛みを伴いますので、海中で触らないようにご注意を!
◎主なアナサンゴモドキの仲間
ヒメアナサンゴモドキ、カンボクアナサンゴモドキ、ヤツデアナサンゴモドキ、ホソエダサンゴモドキなど
ダイビングでよく見るソフトコーラル
押さえておきたい3つの仲間
ソフトコーラル(軟質サンゴ)には、ヤギの仲間(ヤギ目)、ウミトサカの仲間(ウミトサカ目)、ウミエラの仲間(ウミエラ目)という3つのグループがあります。国内外のダイビングではエリアに多少の差はあるものの、ヤギやウミトサカの仲間に比較的よく会うことができます。
ソフトコーラルはポリプの胃腔内を放射状に仕切る8個の隔膜があり、8本のポリプを持つ「八放(はっぽう)サンゴ」なのですが、ハードコーラルは「六放(ろっぽう)サンゴ」でつくりは大きく異なります。また、ハードコーラルよりもソフトコーラルのほうが種類が多いのです。
ヤギの仲間

真紅の枝を広げるリュウキュウイソバナ。白いポリプが開くと全体が白っぽくなります
Photo by Marine Photo Library
言葉で説明すると動物のヤギ(山羊)を連想してしまう人も少なくないのですが、ソフトコーラルの3つの仲間のひとつ。“イソバナ”“ウミウチワ”などの名前がつくものが多いのが特徴です。
その名のとおり、ウチワのような形をしたものや、大きな幹から枝を伸ばし花のようなポリプを咲かせているものなどがあります。また、ムチのように1本1本が長いムチヤギと呼ばれる仲間もあります。イソバナ、オオイソバナ、イソバナモドキなど種類は豊富なのですが、見ただけではなかなか判別しにくいのがダイバー泣かせともいえます。
ウミトサカの仲間

淡いピンク色のポリプが花のように美しいウミトサカの仲間
Photo by Marine Photo Library
透き通った白色の幹に花のようなポリプをたくさんつけた枝を広げるホソエダトゲトサカ、エナガトサカといったチヂミトサカの仲間をはじめ、ウミトサカの仲間もとても種類が多く、見分けがなかなかつかないのが特徴です。“フトヤギ”と呼ぶ人もいます。
ほかにトゲトゲトサカ、オオトゲトサカ、シロバナウミイチゴ、オオミナベトサカなどがある。
ウミエラの仲間

ウミエラの仲間が群生する珍しいエリアも 撮影地/房総半島 波左間海中公園
Photo by Marine Photo Library
ウミエラの仲間にはウミエラの仲間以外にウミサボテンの仲間も属しています。
ウミエラはポリプが開いたときのエダの貼り具合が鰓のような形状をしているのが特徴です。砂地から単独で立ち上がっているものが多く、その際はとても美しいのですが、捕食していないときや水温が低いときなどはだらっと萎れていることもあります。よく珍しいエビが付いていることがあってフォト派に人気です。
種類としてはマダラヤナギウミエラ、シロバナヒメウミサボテンなどがあります。
私たちダイバーを楽しませてくれるサンゴについて、もっと知りたくなりますね♪
次回をお楽しみに。
(デスク/後藤ゆかり)








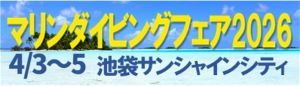


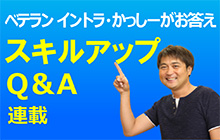

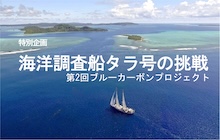
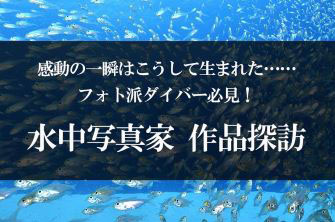






 マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!
マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!