テツ先生の新・海のいきもの
連載第3回 イトヨリダイの瞬間移動?!

東海大学海洋学部海洋生物学科准教授でダイビングインストラクターのテツ先生が「海のいきもの」観察の楽しさを語る連載。第3回は高級食材としても人気のイトヨリダイ。若い個体は夏から秋、ナイトダイビングで見られますが視界から瞬時に消え‥‥テツ先生がその種を明かします。
※2025年11月の情報です
和食、フレンチ、東南アジア料理でも人気の魚

イトヨリダイ 英名:Golden threadfin bream 撮影地:三保真崎 水深25m 体長40cm
ナイトダイビングで見つけたイトヨリダイの成魚。イソメをくわえ、釣り具に掛かった状態だったので、撮影後に釣り針を外してリリースしました。
Photo by Takashi Tetsu
スズキ目イトヨリダイ科の魚である本種は、和食からフレンチ、東南アジアの食卓にも並ぶ魚食や魚好きには掛け替えのない魚と言えるのではないでしょうか。時期によっても変わりますが、目利きの店員がいて仕入れが安定しているスーパーマーケットの鮮魚コーナーでは、週に1度くらいは陳列棚で見ることがあります。
写真のように体側に5本の黄色い縦線(魚は頭部を上方とし、尾に向かう線を縦と考えます)があり、これが本種の特徴です。近縁のソコイトヨリは腹部に同じように黄色いラインがあることで見分けがつきますが、かなりマニアックな店員のいる鮮魚店でなければ、混在して販売されているようです。
暗くなると出てくる天邪鬼(あまのじゃく)

イトタマガシラ 英名:Japanese whiptail 撮影地:三保真崎 水深18m 体長12cm
Photo by Takashi Tetsu
そんなイトヨリダイですが、実はイトヨリダイ科の中で優位に種が多いのはタマガシラと名前の付く仲間たちなのです。イトヨリダイを調べようと思い魚類図鑑を開いてみると、フィールドで撮影されたキツネウオの仲間から始まって、タマガシラの仲間が続き、ページをめくってようやく本種にたどり着くと、標本写真が主体となっていて、少し気持ちがなえます(笑)
イトヨリダイ属の魚は国内に9種が存在し、その大半は南方種となります。先に挙げた2種以外では、ヒライトヨリ、モモイトヨリ、ニホンイトヨリ、シャムイトヨリ、ジャバイトヨリ、トンキンイトヨリ、ヒメイトヨリです。
基本的に、砂泥や泥底を好むため、タイバーの得意とする青くて澄んだ清らかな透明度の場所では観察が難しく、また水深はそれなりに深く、更には暗くなると出てくる天邪鬼(あまのじゃく)な性質なので、通常のダイビングではお目にかかる機会は極端に低いと思います。それでも、夏から秋にかけてのナイトダイビングであれば、体長15㎝程度の若い個体に遭遇する可能性は高くなります。
目の前から瞬時に消える種明かし

イトヨリダイの幼魚 撮影地:三保真崎 体長7㎝ 水深23m
Photo by Takashi Tetsu
イトヨリダイの幼魚は5月後半くらいからナイトダイビングで観察され始めます。成魚ほどギラギラしていませんが、色彩の淡い感じと、体の大きさとはアンバランスな大きな目が幼魚らしい可愛らしさを演出しています。私(テツ先生)が初めて観察した時は、海に金魚が沈んでいるんじゃないかと思ったほど、泥の海底で目立っていました。
イトヨリダイは幼魚のうちは、泥のくぼ地や他の生物が掘った巣穴を間借りしたり、緊急避難に使ったりすることがあります。もう少し大きくなると、軟らかい泥底であれば勢いよく海底に突進して泥の中に逃げ込みます。それまで私は、成長過程にある15cm程度のイトヨリダイが目の前から瞬時にいなくなるのを何度も目撃していたので、すでに成魚のように一瞬で消えるほどの速度で泳ぐ能力を獲得しているのだと勘違いをしていました。しかし、ある日、泥底に潜り切れずに半身が見えていた個体を発見したことで、瞬時に消えるトリックの種明かしができたのです。
ダイバーの皆さんも、海のいきものをじっくり観察することで、さまざまな謎を解明することができるかもしれませんね。
Profile
鉄 多加志
Tetsu Takashi
1965年(昭和40年)生まれ 静岡市出身
東海大学海洋学部 海洋生物学科准教授

ダイビング歴41年、潜水時間約1万3800時間。
国内70数カ所、海外20数カ所を含む約100カ所で潜っている。「ひとつの知識と経験が、同じ場所の同じ風景、生物をもっと魅力的にする」というモットーの下、同じ場所に潜って観察を続けるダイバーで、潜水歴の約8割は三保真崎。大学でも、「好奇心を持ち続けることで、同じ風景や生きものが同じように見えることはない」という観点で履修学生を指導している。
専門は潜水法で「浅海域での長時間潜水時におけるEANガス使用の研究」、「水中遺跡(沈船)潜水調査における安全対策の検討」「水中遺跡(沈没船)調査における安全な潜水方法の研究」(いずれも東海大学海洋研究所研究報告)をはじめ研究論文は多数。
主な著書(共著)に、オーシャンエクササイズ、駿河湾学、海洋考古学入門(いずれも東海大学出版)、THE DEEP SEA(静岡新聞社)、図版 世界の水中遺跡(グラフィック社)などがある。


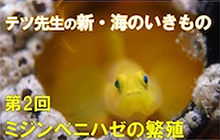


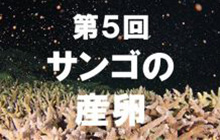






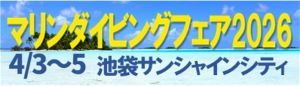


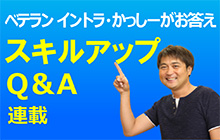

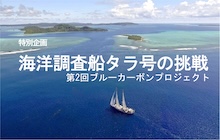
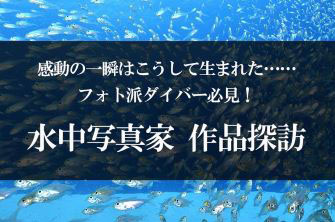






 マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!
マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!