第2回 エイの仲間

第2回 エイの仲間Rays
エイの仲間は、サメの仲間などとともに軟骨魚類というグループに所属し、一般の魚類(硬骨魚類)とは区別されている。魚はいろいろな形で分類されるが、 魚類から次に分かれる大きな分類がこの硬骨魚類と軟骨魚類なのだ。世界に1000種前後を数える軟骨魚類のうちエイは約600種、平べったい体と大きな胸 ビレを持ち、海底近くに生息するものが多い。
人気のあるエイの仲間といえば、やはりマンタが一番だろう。ダイバーならずともその名前を聞いたことがあるはずだ。「泳ぐ」というより、「はばたく」と いう言葉が似合うその姿は、多くの人々を魅了している。エイの仲間の多くは、温厚でおとなしい性格をしているので、そんなところも親しみやすい理由なのか もしれない。

エイの仲間
種類と生息場所
日本で見られる仲間たち

<オニイトマキエイ>
世界最大のエイで、大きな胸ビレをはばたくようにして優雅に泳ぐ姿は圧巻。ジンベエザメ同様にプランクトン食性で、巨体にも関わらずおとなしい性格をしている。
【見られる海】
全世界の亜熱帯から熱帯の海域、日本では沖縄や小笠原、しばしば伊豆半島辺りまでやってくる

<マダラトビエイ>
背面は淡いブルーグレーに白い斑点模様、腹部は真っ白ととてもきれいな配色をしている。砂の中に潜む貝や甲殻類などを捕食するため、しばしば海底で砂を掘るような行動をとる。
【見られる海】
全世界の熱帯から温帯の海域、日本では本州中部以南

<アカエイ>
日本近海で普通に見られる、いかにもエイらしい姿のエイ。体が淡いオレンジ色で縁取られていることで、他種と見分けられる。砂泥中の小動物を好んで食べる。
【見られる海】
南日本沿岸、朝鮮半島、台湾、中国の沿岸の砂泥域

<シビレエイ>
丸っこい体、背ビレのついた太い尾が特徴。胸ビレに発電器官を持つ。50~60ボルトほどの電流をつくることができ、小魚や底生動物をマヒさせて捕食する。
【見られる海】
本州中部~東シナ海、中国、フィリピン

<サカタザメ>
尖った鼻先とスペード形の体形が特徴でとても覚えやすい。100m以深の深場に生息するといわれているが、伊豆半島などでは浅場でも見られる。英名は“ギターフィッシュ”。
【見られる海】
南日本~南シナ海、砂底や砂泥底の海底を好む

<ブルースポテッドスティングレイ>
背中の青い斑点がきれいで、「アオマダラエイ」という仮称がある。サンゴ礁の浅場に生息し潮だまりにいることもあるので、スノーケリングでも出会うことができる。
【見られる海】
インド洋、紅海、中・西部太平洋の熱帯域
おさかなコラム
これってサメ?それともエイ? 悩んだときの見分け方

“サカタザメ”は前述のとおりエイの仲間。名前にサメがつくのにエイの仲間とは、なんともややこしい生き物だ。「平べったい体形だからエイ!」と思って いると、下のカスザメの写真のように間違えてしまうので要注意。なぜなら、サメの仲間の中にもエイのように平べったい体をした種がいるからだ。
サメの仲間とエイの仲間を見分けるポイントは、体形ではなく鰓孔(さいこう)の位置。鰓孔とはいわゆるエラの部分で、その位置が腹部かそれとも体側かと いうことで判断する。ちなみにエイの仲間は鰓孔が腹部にあるとされている。もしもダイビング中に「どっち?」と悩んだら、鰓孔の位置が体側にあったらサメ と覚えてほしい。

エイみたいに平べったい体形だけどサメの仲間
カスザメ

名前に“サメ”がつくけどエイの仲間その1
ウチワザメ

名前に“サメ”がつくけどエイの仲間その2
トンガリサカタザメ
水中撮影のポイント
一度は撮りたい!! マンタの撮り方

ダイバーなら一度は会いたいマンタは、世界最大のエイで体長6mにもなる個体もいる。雄大にはばたいて泳ぐ姿は圧巻で、水中撮影の被写体としても人気だ。マンタはクリーニングステーションと呼ばれる根に集まってくるので、じっくり観察・撮影をすることができる。
マンタ撮影の一番のポイントはとにかく待つこと。マンタがいたからといって、どんどん追いかけてしまうのは厳禁!!あらかじめ撮影に適した場所に待機し、マンタが来るまで待とう。これがマンタ撮影の鉄則だ。
いろいろな撮り方に挑戦

1.下からあおって撮る
マンタ撮影は下から撮るのが基本。マンタが向かってくるところを下から撮影できれば、写真はばっちり。通り過ぎた後の後ろ姿になってしまうと迫力が欠けてしまう。

2.マンタのシルエットを出す
あおって撮るときに、太陽を入れるようにして、シルエットでマンタを表現してみよう。一味違った写真に仕上がるはず。このとき、フラッシュは発光禁止にしておくこと。

3.マンタの迫力を出す
全身を写真に入れることにこだわると、どうもマンタが遠くなってしまい迫力がでない。ヒレがフレームアウトしてもいいのでとにかく寄ってみよう。










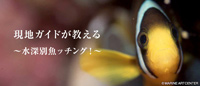






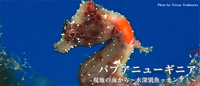
























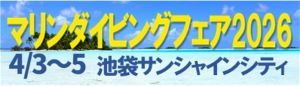


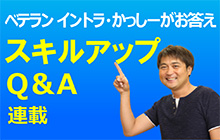

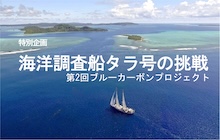
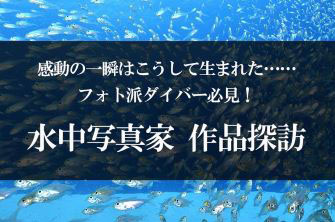






 マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!
マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!