- ホーム
- 海の生き物
- 【連載】海のいきもの
- 第60回 アカククリとツバメさんトリオ~前編
海のいきもの
第60回 アカククリとツバメさんトリオ~前編

サンゴ礁でよく見られるツバメウオの仲間は、ユーモラスな姿とスローな泳ぎで人気者。今回はアカククリをクローズアップしつつ、よく似た4種類の見分け方を紹介します。
●構成・文/山本真紀(2019年10月制作)
アカククリもツバメウオの仲間です
丸っこい体と小さな口が印象的なツバメウオの仲間は、マンジュウダイ科というグループに属している。日本には2属5種が生息。そのうちマンジュウダイという種類はダイバーとほとんど関係がないので、今回はスルーで。
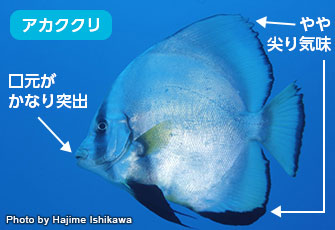
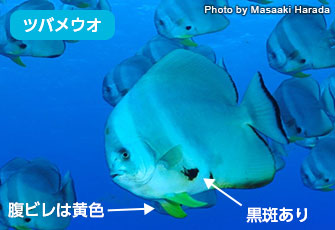
最もポピュラーなのはツバメウオ(撮影/沖縄・久米島)。サイズもそこそこあり(30cm前後)、大群をつくる。驚かさなければすぐそばまで寄れるから、水中モデルにもぴったりだ。そのツバメウオのソックリさんがアカククリ(撮影/沖縄・石垣島)。単独か数尾程度で、大きな群れにはならない。不思議な和名の由来は後ほど。
●識別ポイント:ツバメウオは胸ビレ後方に黒斑があることで、他のツバメウオの仲間と区別できる。アカククリの特徴は少々わかりづらいのだが、口元がかなり突出していること。
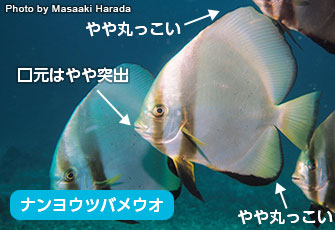

海外のサンゴ礁でよく出会うのがナンヨウツバメウオ(撮影/フィリピン)。大きな群れをつくるところはツバメウオと同じだが、黒斑がないことで見分けられる。アカククリにもソックリで、特に若魚(写真)ではどっちなのか迷う。ミカヅキツバメウオ(撮影/マレーシア)も日本よりは海外でポピュラー。群れは小さめ。
●識別ポイント:ナンヨウツバメウオの口元はやや突出し、背ビレと尻ビレの後端はアカククリと比べると比較的丸っこい。ミカヅキツバメウオは口元がほとんど突出しない。
アカククリが昇る大人の階段




ツバメウオの仲間は成長段階によって姿を変える。4種類の中でも特にダイナミックに「変身」するのはアカククリ。とても同じ種類とは思えない。これらのステージを全部見れたら(撮れたら)、超ラッキー。
①これが幼魚! 和名の由来は一目瞭然。この時期は岩の亀裂や隙間の奥などに潜んでいて、意識して探さないと見つからない(探しても空振ることが多いけど)。大きさ2~3㎝。
撮影/インドネシア・レンべ
②これで8㎝前後。この時期、幼魚の各ヒレが長く伸長するのは他のツバメウオたちも同様。
撮影/インドネシア・レンべ
③かなりアカククリっぽくなってきたが、ヒレの縁にまだオレンジが残る。
撮影/沖縄・ケラマ
④ほぼ成魚と同じ姿だが、まだちょっとヒレが長め。特徴である突き出た口がよくわかる。
撮影/沖縄・石垣島
バックナンバー
- 第59回 季節来遊魚のシーズン~Part3
- 第58回 季節来遊魚のシーズン~Part2
- 第57回 季節来遊魚のシーズン~Part1
- 第56回 もうすぐ七夕!~星の名がつく魚たち
- 第55回 アシカとアザラシ
- 第54回 ダイビングで会える特撮ヒーロー
- 第53回 海の中の桜見物
- 第52回 甘~い、お名前
- 第51回 海の「うり坊」たち
- 第50回 変てこりんなナマコたち
- 第49回 サンゴ礁を脅かすものたち
- 第48回 食べ物としてのサンゴ
- 第47回 隠れ家としてのサンゴ
- 第46回 クリーナーシュリンプの話
- 第45回 コレが自慢!おサカナ何でもTOP3
- 第44回 見栄え重視!おサカナ何でもTOP3
- 第43回 カクレクマノミとニモの話
- 第42回 ソックリさん inモルディブ&沖縄
- 第41回 歩くウオたち
- 第40回 パンダな魚たち
- 第39回 海の天狗とか矢柄とか
- 第38回 タツノオトシゴ&ヨウジウオ
- 第37回 ニシキフウライウオと、その仲間
- 第36回 ミナミハコフグと、その仲間たち
- 第35回 まぎらわしい名前~「仲間じゃないよ」編
- 第34回 夏といえばスプラッシュ!~イルカ~
- 第33回 超大物アイドル登場~マンタ~
- 第32回 アシカと、その仲間たち
- 第31回 アオリイカの産卵シーズン
- 第30回 ご近所のハナダイさん
- 第29回 魚の権兵衛さんたち
- 第28回 鬼にまつわる魚たち
- 第27回 真冬のアイドル、ダンゴウオ
- 第26回 クリスマスカラーの魚たち
- 第25回 ニッポンの冬、チャガラ&キヌバリの季節
- 第24回 こんなところに「ニセ目玉」
- 第23回 「オランウータンクラブ」って何だ?
- 第22回 ニシキウミウシの色彩変異
- 第21回 ドリーとその仲間たち
- 第20回 2・3・4のリュウキュウスズメダイ
- 第19回 イバラカンザシ~美形モデルの正体
- 第18回 コバンザメ~「刺身のつま」に非ず!
- 第17回 寄り添う者たち
- 第16回 アカヒメジ~白黄なのに何故に赤?
- 第15回 “キンメ”と“スカテン”の見分け方
- 第14回 似てない親子~人気者でいこう!編
- 第13回 似てない親子~性転換&ナワバリ編
- 第12回 似てない親子~マネっこ編
- 第11回 ヤドカリと、その仲間たち
- 第10回 最高のパーフォーマー、その名はイカ!
- 第9回 ハゼとテッポウエビの共生
- 第8回 危険なアイツ編
- 第7回 クリーニング編
- 第6回 初夏の「卵」ウオッチング編
- 第5回 擬態編
- 第4回 ウミウシ編
- 第3回 ミノカサゴ編
- 第2回 銀色回遊魚 大型アジ編
- 第1回 ウミガメ



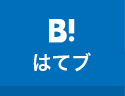
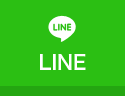



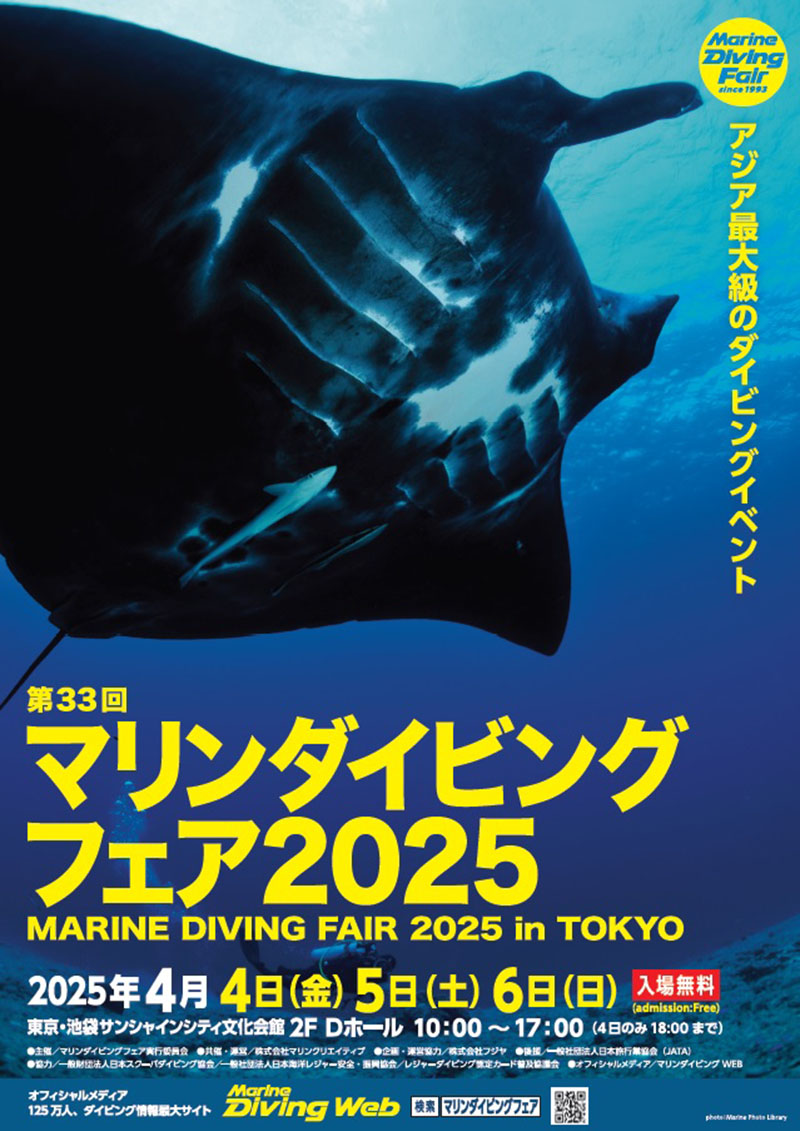












 GULL3点セット+GULL&SCUBAPRO オリジナルボトルをプレゼント!
GULL3点セット+GULL&SCUBAPRO オリジナルボトルをプレゼント!