- ホーム
- 安全ダイビング
- STOP! 潜水事故
- CASE89 久しぶりで緊張のあまり…
STOP! 潜水事故
CASE89 久しぶりで緊張のあまり…

ダイビングに限らず事故はつきものではあるが、最初から最後まで何事もなく安全に楽しめてこそ、本当のレジャー。 ダイビングの場合、潜水事故というと死に至るケースも少なくない。 そして多くの人が「他人事」と思っているフシもあるけれど、ふとした気の緩みやちょっとしたケアレスミスで潜水事故が起こることも。 明日はわが身。 もう一度基本を振り返る意味でも、ぜひこの連載を参考にしていただきたい。
CASE89 久しぶりで緊張のあまり…
今回の潜水事故の原因
- バディ不遵守
- 身体拘束
- 監視不十分
- 器具の不備・取り扱い不注意
- 体調の不注意
- 技量の未熟
- 気象・海象の不注意
- エア確認不注意
- その他
その日1本目のダイビングのためにボートで出港したAさん。10分ちょっとしてダイビングスポットに到着、船上でダイビングガイドがブリーフィングをした後、Aさんを含むゲストの6名を前後で挟むような形でダイビングを開始した。水深10mぐらいの海底の少し上を約50mほど移動した、水深15mぐらいのところでフィッシュウオッチングをしていたが、20分過ぎにAさんがパニック状態に。これに気づいたアシスタントガイドがAさんを連れて浮上した。Aさんは浮上後、心肺停止状態だったが、海面で応急処置を施したことで意識が戻り、船ですぐに港に戻った頃には完全に意識は回復した状態だった。念のため、救急車で搬送した病院では軽い溺水と診断された。
Aさんは久しぶりのダイビングのため緊張していたせいか、耳ぬきが不調で不安がどんどん膨れ上がっていったとのこと。
![]() 直接の原因パニック
直接の原因パニック
対処法
この夏も水の事故が多く、ダイバーの悲しい死亡事故も届いている。心よりご冥福を申し上げます。
さて、今回の事故例は事故者Aさんが意識が戻り、その原因が明らかになっているので分析もしやすいのだが……。
まずAさんは耳ぬきが不調にもかかわらずそのまま海底近くをみんなと泳いでいったことが問題。
耳が抜けないと思った時点で少し水深を浅くして、耳ぬきを再度行い、耳が抜けてから再び潜降してみんなと合流すべきだ。先頭を行くガイドのほかに、しんがりにもう一人アシスタントガイドがいるわけだから、その人に見ていてもらうことはできたはずだ。それ以前にゲスト6人で潜っていたそうだが、バディはいなかったのだろうか? ガイドについていけばいいというスタイルだったように見受けられてしかたないのだが、本来であればバディと一緒に潜って、Aさんの耳ぬきまで待ってもらいながら、ダイビングを進めていくべきだった。
耳ぬきができないままに潜るとどんなに大変かは、近日アップしている「耳にまつわるダイビングトラブル」でも紹介しているけれど、いいことなんて一つもない。
何人ものグループで潜っていると、先頭のガイドからはぐれないようにしなければいけない、みんなについていかないといけないといったプレッシャーがかかるのもよくわかる。そんな経験を持っている読者が多数なのではないかと思うけれど、耳ぬきができない状態で無理やり潜ってもAさんのように最後までもつはずがない。
ということで、まずはバディ、それが無理なら後方のガイドに見てもらいながら、自分のペースで耳ぬきをして少しずつ潜降していくべきだった。
実際水深はさほど深くないところではあるけれど、浅いところほど圧力の変化は大きいので、耳ぬきは何度も必要となる。このことを覚えていてほしい。
アシスタントガイドが気づき、急浮上するAさんをずっと見ていてくれて海面でも応急措置をしてくれたので、助かったものの、タイミングを間違えれば死亡に至ることもある事故だ。
1)無理なダイビングをしない(耳ぬきができないまま潜降したり、ダイビングを続けたりしない)
2)バディシステムを順守する
この2点を守るだけでも事故は防げたはず。
くれぐれもご自分の命は大切にして、安全に潜ることを心掛けていただきたい。
ダイビングは安全に潜ってこそ楽しい!
でも、万が一のとき、あなたはどうしますか??
ダイビングは安全に潜ってこそ楽しい!
でも、万が一のとき、あなたはどうしますか??
ダイビング初心者の方は、ダイビングは怖いものと思っている方も多いと思います。実際は、基本手順やルールを守って潜れば、それほど怖がることはないレジャースポーツです。
また、ダイビングは海という大自然と向き合います。
だからこそ、「水中で体験した感動は忘れられない!」、「人生を変えるほどダイビングは素晴らしい!」と感じるダイバーが多いのも事実です。
しかし、自然が相手のスクーバダイビングですから、100%安全なんてことはありません。万が一のときあなたはどうしますか?
そんな時、DAN JAPANがあなたをサポートします。
DAN JAPAN
一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会
TEL:045-228-3066
FAX:045-228-3063
Email: info@danjapan.gr.jp
https://www.danjapan.gr.jp/
〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町4-43
A-PLACE馬車道9階

バックナンバー
- CASE141 急に吐き気を催し急浮上
- CASE140 フィン装着に手間取り呼吸が不安定に
- CASE139 バディダイビングで体調急変
- CASE138 パニックで急浮上
- CASE137 海外でサメに頭を咬まれ裂傷
- CASE136 寒さで浮上中、海水誤飲、パニックに
- CASE135 初ドライスーツで吹き上げ。帰宅時に半身麻痺に
- CASE134 ダイビング事故の多くは水面で起きる
- CASE133 ダイビング中、耳元で何かが炸裂!
- CASE132 ボートダイビングでラダーに指を挟み大けが
- CASE131 アンカーが外れ漂流。そして行方不明に
- CASE130 他のダイバーと接触しレギュが外れてパニックに
- CASE129 水深40m超でパニック
- CASE128 振り向いたらバディがレギュを外して暴れていた
- CASE127 インフレーターが外れてパニックに
- CASE126 バディを見失いパニックに
- CASE125 二日酔いで潜ってケガ
- CASE124 オクトパスブリージングでパニックに
- CASE123 仲間とはぐれ陸で倒れていた
- CASE122 残圧確認がいい加減でエア切れ
- CASE121 ウエイト調整ができずに急浮上
- CASE120 スノーケリング中に海水を飲んで意識不明
- CASE119 【考察】ドリフトダイビングの危機対処法
- CASE118 初心者が緊張と疲労で過呼吸に
- CASE117 勝手に浮上して漂流
- CASE116 緊張すると口がこわばる癖から海水誤飲で意識不明
- CASE115 ダイビング器材の不具合が原因で溺水!?
- CASE114 セルフダイビングではぐれ…。くも膜下出血で帰らぬ人に
- CASE113 岩をつかみそこねて流される
- CASE112 トラブル続出で溺れる
- CASE111 ブイのロープに急変! そのとき
- CASE110 リーフカレントにはまり漂流
- CASE109 突然レギュレーターを外してパニックに
- CASE108 60代男性ダイバーがダイビング中に体調不良に
- CASE107 ディープダイビングで減圧症の疑い
- CASE106 大物出現!で猛ダッシュするも取り残されてパニックに
- CASE105 ダイビング中、息苦しくなり意識朦朧に
- CASE104 講習中に海水を誤飲
- CASE103 ディープ潜水で減圧症に
- CASE102 ボートと接触
- CASE101 フィンを履く時に転倒して溺水
- CASE100 エア切れで定置網に絡まる
- CASE 99 レギュ故障で緊急浮上するも
- CASE 98 エントリー後行方不明に
- CASE 97 繁忙期のダイビングでパニック
- CASE 96 バラバラにエントリーしてロスト
- CASE 95 アドバンス講習中に急浮上
- CASE 94 冬の海で体調異変
- CASE 93 短すぎる水面休息で減圧症
- CASE 92 顔色が悪かったのにダイビングを開始
- CASE91 浮上後、大波でパニックに
- CASE90 あっという間にエアを消費して…
- CASE89 久しぶりで緊張のあまり…
- CASE88 ダイビングボートが座礁
- CASE87 タンクのバルブの戻し過ぎ
- CASE86 うねりで顔面強打
- CASE85 水深28mでの水中撮影後、減圧症に
- CASE84 冷水海でフリーフローが仇となり…
- CASE83 空気がBCに入らず溺水
- CASE82 無理矢理ダイビングをして漂流
- CASE81 冬の海で意識不明に
- CASE80 ダイビング後、頭痛が止まらない
- CASE79 レギュが外れ、パニック!
- CASE78 水面移動が危ない!
- CASE77 体験ダイビングで絶対してはならないこと
- CASE76 透視度3mでバディとはぐれ、漂流
- CASE75 偽ダイバーのダイビング事故
- CASE74 指示を守らず漂流
- CASE73 潜水後ろれつが回らない
- CASE72 洞窟で迷子に
- CASE71 浮上中、異常行動
- CASE70 ツアーダイブで単独行動
- CASE69 乗っていたボートが転覆
- CASE68 助けてくれたバディが事故に
- CASE67 朝まで飲んで潜ったら
- CASE66 水中で大笑いしたら、海水が!
- CASE65 スノーケリングで溺死
- CASE64 オーバーウエイトと過呼吸でパニックに
- CASE63 母子ダイビングでロスト
- CASE62 ボートのへりから落下
- CASE61 ドライパニック
- CASE60 生活習慣病てんこもりの人が20年ぶりに潜ったら……
- CASE59 突然のめまい
- CASE58 マスク脱着訓練中に急浮上
- CASE57 潜水中にスノーケルをくわえ…
- CASE56 魔のトリプルトラブル
- CASE55 浮上後、レギュを外したダイバーに危機が
- CASE54 セルフダイブで別行動の末……
- CASE53 エグジットの際、うねりで骨折
- CASE52 突然姿を消したダイバーが水中で倒れていた!
- CASE51 大量のエアを吐き体調不良に
- CASE50 病後のダイビングで潜水病に
- CASE49 リーフカレントで戻れず漂流
- CASE48 ウエイトを1kg外したら…
- CASE47 フィンが外れて焦ったあまり…
- CASE46 エンジンがかかっているボートに接触
- CASE45 ダイビング中、差し歯が抜けた!
- CASE44 ダイビング中、呼吸困難
- CASE43 うねりで顔面強打
- CASE42 浮上後、意識朦朧に
- CASE41 タンクのバルブ開け忘れ
- CASE40 潜降中に行方不明
- CASE39 咳き込んで海水を飲み、パニックに
- CASE38 ダイビング中、低体温症に
- CASE37 カメラが岩に挟まってエア切れに
- CASE36 ダイビング中に天候急変、浮上後流される
- CASE35 フリーフローと溺れ
- CASE34 1月の海で減圧症
- CASE33 撮影に夢中になりエア切れ
- CASE32 エアの早い友人を先に上げてダイビングを続行し、漂流
- CASE31 ドライスーツ着用でパニックに
- CASE30 フィッシュウオッチング中にパニックに
- CASE29 ダイビング中に気分が悪くなり病院搬送
- CASE28 エア切れで漂流
- CASE27 海洋実習中、海水を飲み込み、死亡
- CASE26 BCに空気が入らずパニックに!
- CASE25 6月、北の海で70代女性が意識不明に
- CASE24 マスクに海水が浸入して大パニック!
- CASE23 水深40mを潜り、減圧症の疑い
- CASE22 BCに空気が入りっぱなしになり急浮上
- CASE21 浮上したら係留していた船がいない!
- CASE20 水深35mでパニックに
- CASE19 残圧がなくなり一人で浮上し、死亡
- CASE18 ナイトダイビングで帰らぬ人に
- CASE17 フリーフローでエア切れに
- CASE16 レギュレータークリアに失敗して・・・
- CASE15 ロープ潜降で1人行方不明に
- CASE14 初めてのダイビングでパニック
- CASE13 一人セルフで帰らぬ人に
- CASE12 ボートダイビングで移動中に骨折
- CASE11 ダウンカレントにつかまり気づけば-40m超
- CASE10 エアがない!→パニックに
- CASE9 ダイビング中に心停止
- CASE8 海中で咳込んでパニック→急浮上
- CASE7 浮上後、体が痺れて目の前が真っ暗に
- CASE6 ボートから逆方向に流され13時間漂流
- CASE5 エアがなくなったダイバーに突然オクトを奪われパニック
- CASE4 水中で迷子になり、死亡
- CASE3 持病を隠して潜水中、突然の体調不良で失神
- CASE2 マスククリアができずパニック!
- CASE1 ダイビング中に息苦しくなり意識不明に



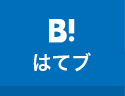
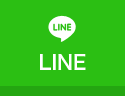
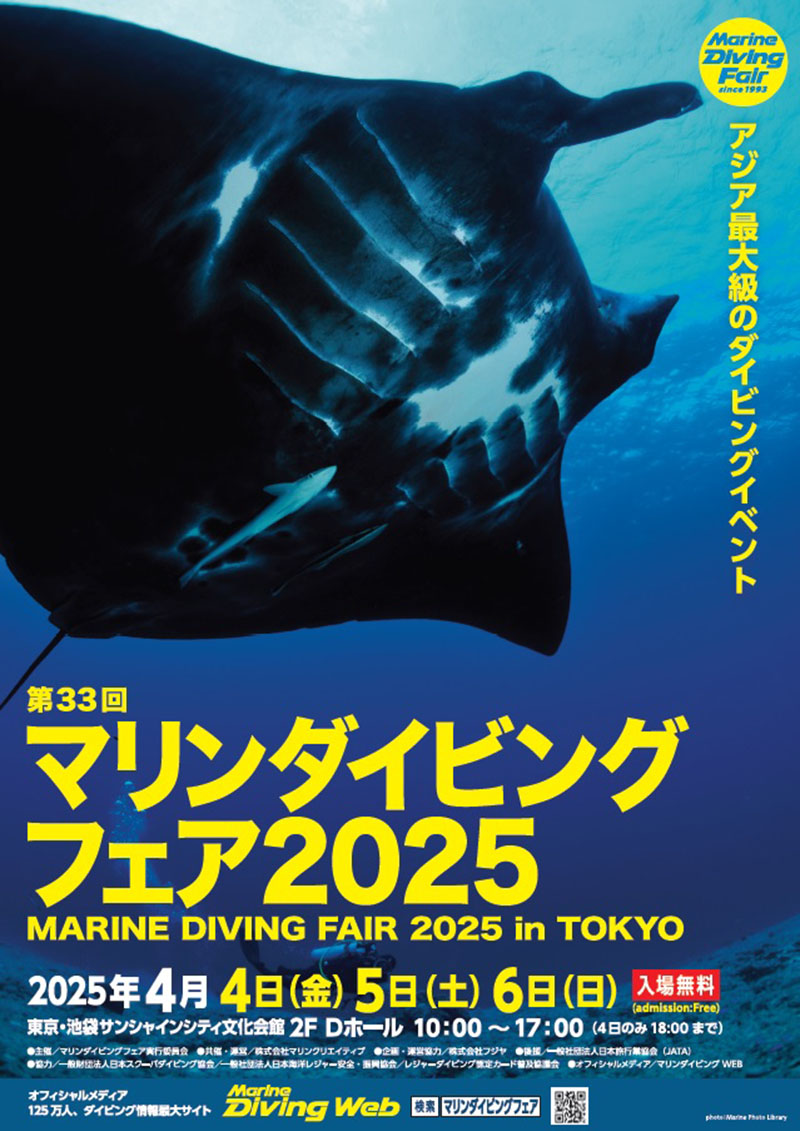


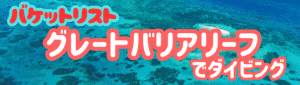
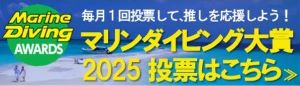










 新刊写真絵本『にこにこモンツキカエルウオ』と海の深層水「天海の水」硬度1000をプレゼント!
新刊写真絵本『にこにこモンツキカエルウオ』と海の深層水「天海の水」硬度1000をプレゼント!